【NTR】黒く染められた特異点~バーゲストの場合~【BBC】 (Pixiv Fanbox)
Content
1話
2話
【NTR】黒く染められた特異点~アルトリア・ペンドラゴン[ランサー/ルーラー]の場合~【BBC】

上記の作品と同じ世界でのお話になりますが、前作を読まずとも問題ないと思われます。アルトリア・ペンドラゴン[ランサー]とアルトリア・ペンドラゴン[ルーラー]は同一個体としての設定で、水着獅子王がデブパワーリフターのような体型の黒人のBBCに完堕ちして恋人のマスターを捨てて永遠の忠誠を誓っちゃうお話です。よ...
3話
【NTR】黒く染められた特異点~虞美人の場合~【BBC】

前々回 前回 日本でも指折りの観光地として賑わう、2017年の由比ヶ浜を舞台にして発生した特異点。 その『黒人崇拝海岸・由比ヶ浜』は、ついにカルデアへ毒牙をかけんとしていた。 微小特異点ではあるために人理へと直ちに与える影響は大きくないものの、観測者であるカルデアに所属するサーヴァントを強制的に...
4話
【NTR】黒く染められた特異点~カイニスとモードレッドの場合~【BBC】
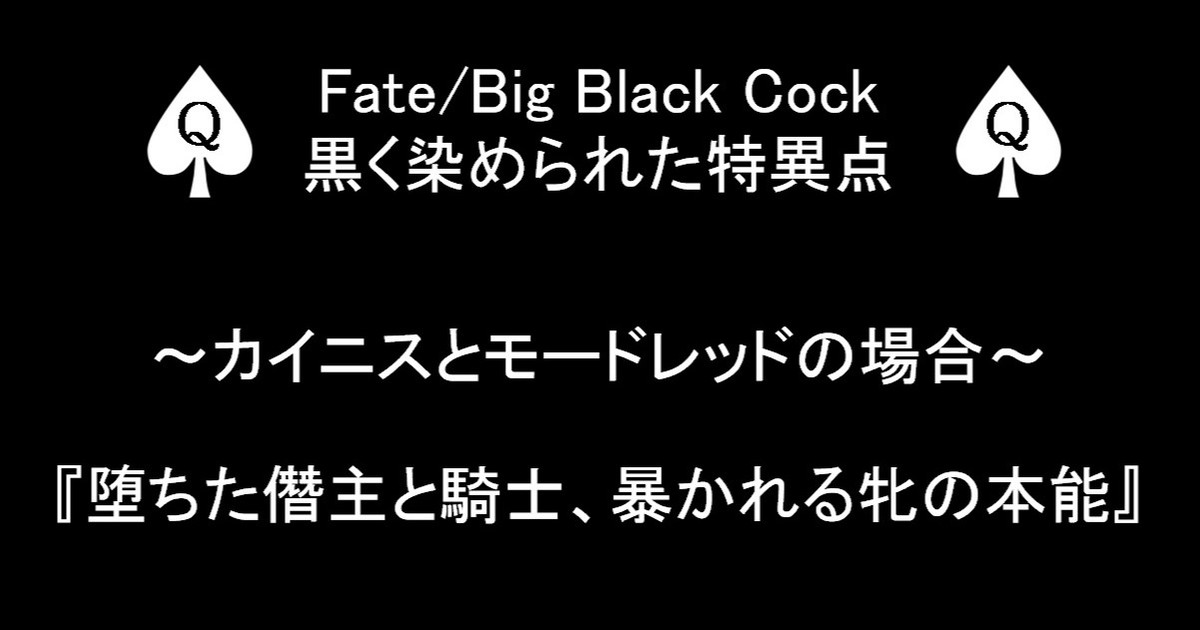
第1話 第2話 第3話 ────────────────────────────────────────────── 『人理継続保証機関フィニス・カルデア』の新たなる拠点、『ノウム・カルデア』。 『人理焼却』という大災害から人理を救い、現在進行系で『人理漂白』という大侵略から人理を取り戻すために奔走している、人類最後のマスター・『藤丸立香』。彼...
5話
【NTR】黒く染められた特異点~マルタの場合~【BBC】

第1話 第2話 第3話 第4話 ────────────────────────────────────────────── 『人理継続保証機関フィニス・カルデア』の新たなる拠点、『ノウム・カルデア』。 『人理焼却』という大災害から人理を救い、現在進行系で『人理漂白』という大侵略から人理を取り戻すために奔走している彼こそが、人類最後のマスター・『...
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
これより語るは一つの結末。
黒い男に染められた、人理を保証する集団のその行く末。
弱きものはお帰りを。
ここは黒き怒張の、王様の海岸線――――。
◆
『人理継続保証機関フィニス・カルデア』の新たなる拠点、『ノウム・カルデア』。
『人理焼却』という大災害から人理を救い、現在進行系で『人理漂白』という大侵略から人理を取り戻すために奔走している、人類最後のマスター・『藤丸立香』。
立香は自身が召喚したサーヴァントである女性たちと体を重ね合わせる関係に、一種のハーレムを創り上げていた。
アルトリア・ペンドラゴン[ランサー]。
虞美人。
カイニス。
モードレッド。
マルタ。
数えればもっと多くの女性の名を上げることが出来るが、思いついた名を列挙するだけでもこれほどの大物英雄が、藤丸立香の寵愛を受けることを望んで夜を共にしていた。
そして、立香は今日もまた昨日とは異なる女とマイルームを共にして、体を重ねているのだった。
「あぁっ❤ マスター、いいですよっ❤ もっともっと、私を気持ちよくしなさい❤」
「ふぎゅぅっ!? むぎ、ぐぐぅ、んぎぃぃぃ~~!?」
大きい女だった。
何が大きいというよりも、全てが大きい女だ。
背丈も。
首も。
肩幅も。
胸板も。
お尻も。
手足も。
骨格も。
体を構成する全てが大きい。
見ることが出来ないのに、恐らく、その体の中に入っている内臓も大きのだろうと思わせるほどの大きな女だった。
だが、『オトコオンナ』と揶揄したくなるような、いわゆる女性的な美を持たないのかと問われると、全くそんなことはない。
その大きな女は、確かに女性だとわかる体の特徴と整った顔立ちが生む女性らしい美しさを持っていたのである。
膨らみを持つように波打つ金色の髪はまるで豊かな土地の小麦畑さながらであり、どこか鋭利な印象を与える切れ長の瞳と高い鼻が作り出す優雅な美貌と合わさって、高貴な気高さを感じさせる類の美しさだった。
顔立ちだけではなく体つきもそうだ。
肩幅も並の男を凌駕するほどに広く、肩から首にかけての盛り上がった僧帽筋や、岩のように固く盛り上がった肩に、バキバキという表現が似合うほどに固く割れた腹筋は確かにとても女性のものとは思えないだろう。
だが、それでもそこについた、大きな女の中で唯一平均よりも小さな美しい小顔と比肩するほどの豊かな巨乳、いや『爆乳』は女性以外のものでもなんでもない、重力に逆らうようにぷるぷると震えながら浮かび上がっていることから弾けるようなハリと柔らかさを感じさせるのだ。
女性らしい大きさと言えば、乳房だけではなく臀部も非常に大きい。
骨格からして大きく拡がっているのだろう、女性によっては命がけになるはずの出産も平気な顔をして終わらせるだろうと感じさせる見事な安産型の巨尻であった。
それでいて割れた腹筋が作り出す、余分な白い肉の一切を排除した、触り心地などのデザイン性などではなく人間という種が持つ機能性を最重視したことで大きな乳房と大きな臀部の間にキュッとくびれた腰を作るという奇跡的なバランスを生み出していた。
見るものが見れば、ビスクドールのような儚さを持った美少女よりも、白い肉で全身を包んだ柔らかな肉体の官能的な美女よりも、強く獣欲を抱いてしまうような強い女だ。
強さと美しさを兼ね備えたこの女もまた、藤丸立香という多くの女と関係を結びついている、俗に言う『スケコマシ野郎』とセックスを行うハーレムメンバーの一人である。
バーゲスト。
『何かしらの巨大な事件などを契機として、全く別の歴史を歩んだ世界』、この『有り得ざる歴史の断片』である異世界のことをカルデアは『異聞帯』と呼ぶ。
その異聞帯の一つである『ブリテン異聞帯』に存在する『妖精國ブリテン』において、妖精女王モルガンから『妖精騎士ガウェイン』の着名(ギフト)を授かった騎士姫である。
マンチェスター領の領主でもある気高い貴族でもある彼女の振る舞いは、非常に理性的で知性に満ちたものだ。
「あぁぁぁっ❤ マスター、マスター❤ たまりませんわ❤ あなたの肉棒が、わたくしのオマンコぉ、こすこすと弱々しく擦っているこの愛らしさ❤ はぁ、もっと❤ もっともっと❤ わたくしが、骨の髄まで犯して差し上げますわぁ❤」
だが、このベッドの上で寝そべっている人類最後のマスター、藤丸立香の足を乱暴に掴んで腰を持ち上げさせ、そのままガニ股になって腰を上下に振っている乱暴な、『逆レイプ』で犯していた。
その言葉は騎士としての凛々しさはなく、放っている言葉を文字に起こして見れば、自領を治める貴族の姫としての気高さを感じさせるが、実際にその声を聞けば性的快感と幸福感に塗れて蕩けきった、『牝の声』だということがはっきりとわかる淫靡なものである。
騎士たらんと努めて纏った鎧を外し、領主であろうと構えたドレスを脱ぎ捨てたバーゲストは、本物のケダモノであった。
カルデアの中では便宜上、『第二再臨』と呼んでいるいつもの黒いドレスはベッドに乱雑に脱ぎ捨てられ、裸体を晒したバーゲストは騎士からお嬢様に変わったように、お嬢様からケダモノへと変貌してしまったのである。
その弱々しささえも愛しく感じる藤丸立香の足首を掴んで、強引に犯してその精を搾り取ろうとするほどには、今のバーゲストは淫欲に溺れてしまっていた。
「ふぎゅぅっぅ! バ、バーゲス、ト! い、いったんとめ、とめて、いぎぃぃぃっぃ!?」
だが、その暴力的な性衝動の発散に付き合わされ、逆レイプされてしまっている立香は溜まったものではない。
腰を持ち上げられたまま、男であるはずの立香よりも遥かに大きいバーゲストの巨体が全力で腰を打ち付けてくるため、それを受け止めるスプリングの役目を果たす腰が壊れそうなほどに負担を覚える。
バーゲストによってガッチリと掴まれた足首は今にも骨が折れてしまいそうなほどの痛みを発しているし、それを嫌って拘束から逃れようと足を動かせばバーゲストはより強く握りしめてくるではないか。
極めつけには、そのセックス自体も激しすぎて立香にとっては快感を飛び越えて苦痛を生み出すものとなっていた。
元々、仮想包茎であった立香の男根はあまりにも繊細で、ピストン運動も弱々しく行わなければいけないほどの雑魚チンポである。
その立香の雑魚チンポを、バーゲーストの筋肉マンコでぎゅぅぅぅっと締め付けながら皮かぶりチンポをむいでいって、普段は包皮の中に隠れている敏感な肉棒を激しく擦り上げていくのだ。
立香は様々な苦痛によって、目の前がバチバチと弾けるような衝撃を受けて、今にも失神してしまいそうになっているほどである。
「あ~……❤ 気持ちいい、気持ちいいですわ❤
されるがままのマスターのなんと愛らしいこと❤ わたくしは、マスターを犯しているとはっきりとわかるのです❤
やはり、好悪に強弱の影響はあれども――真実の愛に、肉体的な強さなど関係ないのだ、と❤
わたくしに勝るところなど何一つないマスターがこれほどまでに愛おしく思えるのは、ああ、『妖精國で起こった惨劇』を、『忘れたい過去』を思い出させつつも……わたくしに本能を越えた理性を感じさせてくれます❤ 愛しています、マスター❤ もっと繋がりましょうっ❤」
「おぉぉぉっっぉお!? ひぎぃぃ、にぎぃぃぃぃぃ!? ふぅぅ、ぅぅぅっ❤ ぐうっぅっっぅぅ!?」
バーゲストは蕩けた表情で余裕たっぷりに、自分が気持ちよくなるために腰を振っている。
しかし、立香は眼球が今にも裏返りそうなほどの痛みに襲われていくのだった。
二人は愛し合ったパートナーでもあるが、しかし、この夜だけを見ればどう見てもバーゲストが立香を強姦レイプしているようにしか見えない状況である。
「ふぐぅぅぅぅぅ!? うぅぅぅっ、ぅぅぅっぅ!? あっ、あぁぁぁっっ!?」
「おっ、おほぉ❤ 震えていますね、マスター❤ 可愛らしくピクピクと、わたくしの筋肉オマンコの中で震えているではないですか❤ 出しなさいっ、今度こそ一滴残らず子宮で迎え入れてあげます❤ その情けない射精ではわたくしの締め付けをかいくぐることが出来ず、未だに一滴として子宮に注げた経験のない弱々しい精液を、わたくしもまた筋肉を蠢かせて受け入れてみせましょう❤ さぁ、イッてください❤ イッて、イッて…………イケぇっ❤❤❤❤」
「むぎゅぅっっぅぅぅぅっぅぅ!?」
どぴゅっ、ぴゅるるっ、ぴゅぅぅ~~……!
「ほぉぉっ~~……❤ あぁ、いい感覚……❤ ふふふ、あっさりとした、水のような精液を出すのですね、マスター❤ 今にもオマンコから流れ落ちてしまいそうなほどに、サラサラとしてますね❤
ですが、安心しなさい❤ このわたくしが今度こそ、力を緩めて子宮で受け入れてあげますわ❤」
「おぉっぉ……ほぉぉ……ふぅぅ、ぁ、ぁぁぁ……ひぎゅ……」
ガクリ、と。
射精と同時に、立香の全身から力が喪われていく。
あまりの強烈な刺激に失神したのだ。
これはバーゲストのケダモノのような合意の上での逆レイプだけでなく、加虐的な美少女・美女サーヴァントとセックスをすれば、立香はこのように容易く失神をしてしまう。
それほどに、性的な弱者なのだ。
「んぅぅ、ふぅぅ……んくぅっ❤」
そんな立香の体を、やっとではあるが、労るようにしてバーゲストはゆっくりと男根を引き抜いていく。
そのオマンコからはチョロチョロチョロという音が出てきそうな形で、サラサラのザーメンがこぼれ落ちていくではないか。
今日もまた、立香の薄々な弱々しいザーメンは、バーゲストの子宮まで届くこともなく、鍛えられた腹筋と尻の筋肉が生み出す強烈な締め付けに阻まれて、このように外へと流れ出してしまったのだ。
これはバーゲスト自身の牝の本能が、『このような弱い雄の子種など受け入れられるか!』と怒りながら撥ねつけていることを意味している。
「あぁ……マスター、なんて可愛らしい……❤ わたくしは、バーゲストはあなたを慕い、愛していますわ……❤」
騎士の時の無骨な言葉遣いとは異なる、優しげで気品のある、それでいて淫らな色を含んだ『お嬢様』としてのバーゲストで、立香への愛を囁いていく。
どれだけ体が立香という雑魚雄を否定しても、バーゲストという女の心は確かに人類最後のマスターである藤丸立香を愛しているのだ。
それはある種、『真実の愛』の一つの形と言えるだろう。
このカルデアにおいては、バーゲストの捕食衝動も治まっている。
何かを乗り越えたわけでもない、立香への愛情に依存をしている歪な関係だが、それでもバーゲストはやっと幸せを享受できているのだ。
そう。
あの特異点――――『黒人崇拝海岸:由比ヶ浜』へとレイシフトをしてしまう、その日までは。
バーゲストは確かに、藤丸立香へと無条件の愛を抱いていたのだ。
◆
『Forgive us. Forgive us. Forgive us our sins.』
ゆるされよ、ゆるされよ。
みだらな我らのつみを、ゆるされよ。
ゆるされよ、ゆるされよ。
あそびはおしまい、股と心を開いてしまえ。
楽しいはずの時間も楽しくないさ。
砂浜が黒く染まるぞ、誘われてしまえ。
今日が終わるよ、さようなら。
今日も終わるよ、いつまでも。
ゆるされよ、ゆるされよ。
みだらな我らのつみを、ゆるされよ。
どうせすべてはあとのまつり。
弱い男なんて捨てちゃいな!
新たに出現した特異点『黒人崇拝海岸・由比ヶ浜』の砂浜におかれたベンチに座り込み、人類最後のマスターである藤丸立香はぼうっとした様子で海を眺めていた。
周囲は騒々しいほどに人々が行き交っており、しかし、現代社会特有の無関心さによって生まれた孤独な空間は、立香に干渉してくるものを生み出さない。
誰もいない草原で感じる孤独と、人で溢れかえった街並みで感じる孤独は、どちらが重いものなのだろうかなんて思いながら、無関心が生む落ち着いた空間の中で立香は思考をまとめていく。
「黒人の犯罪集団が敵、か。そこで聖杯の力を手に入れて、いろんな女の人に暴行をして、奴隷のように扱っている特異点――これ、聞いたらみんな怒り出すよな。頼光さんやアルトリアも、虞美人先輩も、カイニスとモードレッドも、マルタさんも、みんなそういう犯罪者のことを毛嫌いするタイプだし」
この由比ヶ浜特異点へとレイシフトしてから数週間、まるで進んでいなかった調査は、先日のとある『協力者』によって劇的な進歩を見せていた。
立香も厚い信頼を寄せる女性サーヴァントである聖女マルタとともにビーチを探索していた時に、『ドミニク』という善良な一般人が声をかけてきたのである。
そのドミニクは、マルタと同じくカルデアにおいて強い信頼を抱くアルトリア・ペンドラゴン[ランサー]と出会い、この特異点を成立させた『敵』の存在を教えてくれたのだ。
そこで渡された動画には、まるでポルノ作品のように女性を凌辱し、それでいて女性が歓喜に悦ぶ姿が撮影されていた。
女を犯している黒人たちに都合の良すぎる展開は、やはり聖杯の力が関係していると立香に確信させるには十分過ぎる内容である。
やっと手がかりを手に入れたということもあって、ここはこの特異点にレイシフトしてきた全サーヴァントと一度合流をして、その黒人犯罪集団の詳細を調査しようと立香は考えたのだが、ここで一つ問題が起こった。
「なのに、みんなと合流できない……!」
自身の信頼するサーヴァントたちと、全く出会えなくなったのである。
立香は嘆くほかなかった。
源頼光も、アルトリア・ペンドラゴンも、虞美人も、カイニスも、モードレッドも、マルタも。
誰一人として合流することが出来ないのだから。
行く宛もない立香は肩を落としながらこの美しく華やかなビーチへと向かい、こうして砂浜に腰掛けて物思いに耽っていたというわけだ。
「…………黒人の犯罪集団による集団レイプと、そこで気持ち良すぎて性奴隷みたいなことに志願してしまう被害者の女の人たち、か。まるでエロ漫画だよなぁ」
サーヴァントと合流できない立香は、仕方なく現状の情報を整理していくことにした。
と言っても、情報らしい情報は『敵』である黒人集団が、同じ男としては許しがたい卑劣な集団ということしかない。
しかし、思い出しただけでも腹が立つと同時に、下品なことだが少々羨ましくもなってくる。
レイプまがいに女性を犯すということは卑劣なことだが、そのレイプを続けていくうちに女性側が性的快感に溺れていき男へと媚びるようになっていく姿は、女性にとっては唾棄すべき感覚だろうが、『男の歪んだロマン』とでも呼ぶべきものだ。
自分を慕ってくれる美少女たちや美女たちには言えないことだが、立香もそのようなことが出来ればと思わなかったことはない。
「……まあ、俺は俺でみんなに愛される『ハーレム』を作れてるんだよな」
だが、その後に自身の夢のような状況を思い出して、デレレとみっともなく顔を緩めていく。
黒人の集団は聖杯の力を使って女たちを魅了しているが、自分はそんなものを使わずに自分自身の魅力だけでハーレムを創り上げたのだ。
それは、人理を救ったという偉業に並ぶほどに、立香にとっては自慢できることなのだ。
「内容を見た限りだと、こういうこと言っちゃいけないけど、ドミニクさんが持ってきた動画の中にあんまり綺麗な人は居なかったしな……そういう意味でも、俺の勝ちだよね」
正直な話、立香はかなり下衆なことを言っているのだが、それも仕方ない。
藤丸立香は偉大なことを成し遂げたものの聖人ではなく、普通の青年である。
周囲に女の子が居ない状況ならば、異性からは眉をしかめられるようなことを考え出すのは、立香が平凡な一人の人間であることの証明でもあるのだから。
「みんな、俺とのセックスに満足してくれてるみたいだし……なんというか、本当に幸せものだよな、俺って」
だが、この発言だけはいただけない。
今までの発言は一つの『事実』を口にしていただけだったが、この発言は単なる『勘違い』なのだ。
立香とのセックスに満足を覚えているものなど、立香のハーレムの中には居ない。
マルタやバーゲストなどの、立香が性的弱者であることを『愛らしい存在だ』と許容してくれる女性も居るには居るが、それはあくまで妥協に過ぎない。
マルタもバーゲストも、可能ならば貪欲に自分を求めてほしいと思っているのだが、立香はあまりにもセックスが雑魚すぎるために一度射精をしてしまえばぐったりと倒れてしまうから自分からそれ以上を求めないだけだ。
本当のところを言えば、二人のような立香のセックスを優しく受け入れてくれている女性であっても、出来ることならばもっと立香が性的にたくましければと無意識下に、しかし、はっきりと不満を抱いているのである。
それにも気づかずに『俺はハーレムを築いていて、ちゃんとみんなのことを満足させられているぞ!』と思っている立香の、なんと滑稽なことだろうか。
「でも、仕方ないよな。それだけのことはしてきたし、ペニスも大きいし……な!」
あるいは、この特異点の影響で愚鈍化しているのかもしれない。
小指ほどの大きさしかない、粗チンの中の粗チンとも呼べる小ささのペニスを大きなペニスであると称するなど、正気の沙汰とはとても思えないことだ。
だが、それを指摘してくれる心優しいものは居ない。
大勢の人が楽しそうに行き交う海岸で、一人でニヤニヤと笑みを浮かべている立香は目立つ。
周囲の人からヒソヒソと遠巻きにされて、気味悪そうに一定の距離を空けてしまっているのだが、立香はそれにも気づかずにどんどんと『伝説の英雄や偉人を自分の女にしている俺ってすごい!』という半分は事実で半分は妄想の考えで悦に浸るのだった。
そんな立香へと、一人の女性が近づいてくる。
気配を消しているわけではないのだが、それでも妄想に夢中になっている立香は気付くことはなく、結局背中から声をかけてきたのだった。
「ごきげんだな、マスター。なにか良いことでもあったのか? 例えば、自分の女の水着姿を想像している……とかな」
「わわわっ、バ、バーゲスト?!」
そう、バーゲストである。
先ほどまではニヤニヤとしている立香が不気味であるという、言うならば負の理由で目立っていたが、バーゲストが話しかけたことで一転して好意的な理由で注目を浴びだしていく。
それも仕方ないだろう、なにせ、輝かしい美貌を保持しつつも、190センチという女性でなくても長身と呼ぶに相応しい身長と、服をパツンパツンに張り詰めさせた爆乳とデカ尻の持ち主で、さらにはタイトミニスカートから伸びるガチガチの筋肉が詰まった長い脚は、男も女も魅力的に感じる他ない凄まじい体躯なのだ。
男たちはその美貌と爆乳へと情欲に満ちたし線を向けつつも明確に自分よりも強いであろうと感じさせる体格に怖気づき、女たちは凛々しくも麗しい美貌をしながらもどんな男よりも強そうな体格をしていることにうっとりとした憧憬の視線を向けている。
(すっげ~女……マジで隣のガキが情けないぐらいダサく見えるな……いや、あいつに限らず俺でも同じか。脚の長さなんかぜんぜん違うし、そもそも身長が頭一つ分ぐらいの差があるし、あの腹筋からして俺より絶対に喧嘩も強いしな……いい女だけど、一緒に並びたくないな)
(キャー! キャー! なにあの人、すっごいきれいですっごいかっこいい! 女の人なのにすっごい強そうだし……私の超好み! 隣の男の子は可愛い系だけど、本当に並んだらかっこよさの違いが際立っちゃうなー! まあ、どんな人でもあの女の人の引き立て役にしかならないから、あの男の子が悪いわけじゃないけどね)
ただ、そんなふうにバーゲストを見ている人々の中で、男でも女でも共通している考えは、『バーゲストの隣に並びたくない』というものだ。
その美しさも、その強さも、並べば自身の未熟さが際立ってしまい、バーゲストの引き立て役にしかならないとわかってしまうからである。
それなのにヘラヘラと笑っている立香は、ある意味では度胸のある大物と言えるだろう。
「今日の服装……ハワトリアの時のだね。UDKの団長の状態なんだね」
そんなバーゲストの服装は水着姿ではなく、黄色のジャケットと白のミニスカートを身に着けた、いわゆる『レンジャー隊』のユニフォームであった。
ただ、それを身に着けているのがあのバーゲストであるため、まともな服装であるわけがない。
半袖のスカウトシャツが特に顕著である。
胸元は大きく開かれており、その重力に逆らっている爆乳がシャツを大きく盛り上げているではないか。
特に前をボタンで止めるのではなく、裾を伸ばしてヘソより高い位置でギュッと縛っているために、その鍛えられた腹筋ときゅっとすぼめられたオヘソが丸見えになっている。
スカートもまた、同様だ。
太い足と大きなお尻を包み込むにはあまりにも弱々しく短しいスカートで、パツンパツンに張り詰められて膝上何センチ、股下何センチというレベルではなく、『股下0センチ』というレベルである。
今のバーゲストは、足を動かすだけでそのスカートの奥にある衣服が見えてしまうような、活動的なはずのレンジャー隊のユニフォームを卑猥なマイクロミニスカートへと変貌させてしまっていた。
さらに、髪型も動きやすいポニーテールにまとめており、時折チラチラとその太い首に奔るうなじが除き見えるのだった。
「ああ。今の私はUDKバーゲスト……なのだが、少々予定外だ。ここは都市開発が進んでいて自然と呼べるものがないんだ」
この状態のバーゲストは妖精騎士ガウェインでもマンチェスター領主バーゲストでも黒き災厄でもない、森林守護騎士連盟UDKの団長であるUDKバーゲストなのだ。
ちなみにUDKとは、『Union Defence Kinghts』の略称である。
自然保護をモットーとするバーゲストは、以前に夏の特異点を体験した経験からこの特異点でも森林保護を行おうと考えていたのだが、『ハワトリア』と『由比ヶ浜』では大きく事情が異なっていた。
コンクリートジャングルのすぐ近くであるこの由比ヶ浜では、特異点が拡大しない限りはUDKとしての活動を行うことが出来ないのである。
「そ、それならさ! い、一緒に歩かない? 色々と話したいこともあるし、バーゲストは特異点解決の戦力としてもすっごく頼りになるしさ」
「っぅっ~~! も、もちろんだ、マスター!」
立香はそんな手持ち無沙汰なバーゲストをビーチデートへと誘っていく。
その誘いを受けたバーゲストは、UDK団長として凛々しく顔を引き締めていたというのに一瞬で真っ赤に顔を染めた後、輝くような笑みを浮かべた。
それを見た周囲の人物は、あのかっこいい美女が乙女のような反応をしたことに驚愕し、同時に同性も異性も関係なく、胸をドキリと高鳴らせてしまう。
それほどの魅力をバーゲストは持っていたのである。
「あ、いや、今はオフだから……そうですね。少し、リラックスした姿になりましょうか……!」
そんなバーゲストは、無自覚に魅力をどんどんと振りまいていく。
自分がどれだけ女として魅力的なのか、バーゲストはどうやら少々自覚が足りないようだ。
そうして、ポニーテールにまとめていた髪をほどいて『ふぁさぁ』っと長い髪をたなびかせ、そのスカウトシャツとミニスカートをその場で脱ぎだしたのだから間違いない。
「うわ、バ、バーゲスト!?」
スカウトシャツの下が普通の下着ではないかと思っていた立香は慌てふためくが、もちろん、性欲は強くとも貞淑なバーゲストがそのような露出狂のような真似をするわけがない。
そのスカウトシャツとミニスカートの下にあるものは、バーゲストの規格外の巨体でも問題なく着ることが出来る――――『紐ビキニ』なのであった。
だが、それだけではない。
「あ、ああ、水着を着てたんだ……って、バ、バーゲスト!? わ、腋と股間が……!」
「へ? ……なっ、なんで!? 処理はしているはずなのに!?」
この特異点、『黒人崇拝海岸:由比ヶ浜』の影響でバーゲストのただでさえ大きな爆乳とデカ尻がさらに肥大化していることはもちろんのこと、騎士らしく淑女らしく、普段からしっかりと処理を陰毛と脇毛が生えてしまい、それが露出してしまっているのだ。
細かいことを言えばそれだけではない。
僅かではあるが豊満化したの影響だろう、バーゲストのビキニブラは爆乳を完全に包み切ることが出来ず、人よりも少々大きい乳輪が覗いてしまっているのだ。
「さ、さすがにこれはっ……! み、みっともない姿を見せて申し訳ありません! す、すぐにこんな水着はやめますので……!」
「い、いや! 凄く魅力的だよ、バーゲスト! なんかセクシーでかっこいいというか!」
そこで水着を着替えようと考えたバーゲストだったが、立香がストップを掛けた。
普段から貞淑なバーゲストが見せた、下品過ぎるがためにエロすぎる水着姿をもっと見たいと、下劣な雄の欲望を抱いてしまったのである。
こうなると、立香にべた惚れしているバーゲストは断ることが出来ない。
顔から火が出るほどに恥ずかしいが、愛する恋人の要求のために陰毛と脇毛と乳輪が覗いている変態水着姿でビーチを歩くことを決めたのであった。
(~~~! レイシフトするまでは毛の処理が出来ていたというのに! なぜですか!? まさか特異点の影響だなんて言わないでしょうね……! ああ、マスターが水着姿を喜んでくれてるから今さら服を着直す事もできないし、は、恥ずかしい~~!)
(なんだか、いつもよりおっぱいとお尻が大きいような……? それに、真面目なバーゲストが陰毛とか脇毛の処理をしないなんて、変なこともあるものだなぁ……で、でも、凄くエロいから俺は嬉しいんだけどね……!)
あまりの羞恥に視界が狭くなってしまっているバーゲストは、鼻の下を伸ばした情けない顔をした立香が、チラチラと横目でバーゲストの爆乳やデカ尻を盗み見していることにも気づけない。
いや、そんな顔をしているのは立香だけではない。
先ほどまでは背筋をピンと伸ばして歩くUDKバーゲストの凛とした雰囲気に気圧されていた男たちだったが、顔を真っ赤に染めてもじもじと歩いている今のバーゲストならばその強さというものが半減してしまっている。
むしろ、中には謎の蛮勇を振るう人物まで出てきてしまったのだ。
「ねえねえ、お姉さん! 弟くんと一緒なの? お世話して偉いけどさぁ、せっかくの由比ヶ浜なんだから俺と一緒に遊ばない? 弟くんだって、その年令なら一人で大丈夫だって!」
「………………………なんだと?」
すなわち、立香と並んで歩いているナンパを行おうとしたのである。
しかも、愛する立香を『恋人』ではなく『弟』だと認識したのだ。
それはバーゲストにとって敵対宣言、いや、侮辱の言葉にも等しかった。
「私にはこの素晴らしい恋人がいる! 失せろ! 貴様のような男とかわす言葉を出していることすら気持ちが悪くなってくるほどだ! 天地がひっくり返ろうとも、彼の魅力の足元にも及ばない貴様と行動をともにすることなどあり得ない!」
「ひぃ、ひぃぃぃぃぃっ!?」
水着姿となって淑女モードとなっていたバーゲストだが、あまりの怒りに騎士としてのバーゲストが現れてしまうほどだった。
そのあまりの迫力に、ナンパしてきた軽薄な男はしめやかに失禁してしまう。
水着を尿で汚しながら、脚をもつれさせる無様過ぎる動きで立ち去っていくのだった。
(チッ……! あのような雑魚に声をかけられるとは……気を張り詰めろ、バーゲストよ! お前はマスターの恋人、その一人なのだぞ! 全く……なよなよとした体をしている癖に、なぜそのような蛮勇だけが震えるのだ……!)
バーゲストの中から羞恥が吹き飛ぶほどの怒りが湧き上がる。
これがたくましい肉体をした騎士や勇士、戦士がナンパをしてきたのならば別だろうが、先ほどの男は日本人らしい小柄でどこか頼りない体躯の、どう見ても強そうには見えない軽薄な男だったのだ。
強さを重視し、弱さを嫌悪するバーゲストにとっては唾棄すべき存在と言えるだろう。
(…………まあ、なよなよとしているという意味ではマスターも同様なのだがな。訓練をしているはずなのに、一向に大きくならない体はあまりにも情けない。だが、仕方ないだろう。あの気味の悪いナンパ男も、愛しいマスターも、日本人なのだ。日本人は弱くて情けなく、外見だけを見れば、女としては魅力に感じれないものだ……それはもう仕方ない。マスターの内面を知っているから私はマスターに恋をしているだけで、肉体だけを見れば身の回りに近づけることも疎ましいというのが正直なところだがな)
だが、ここでバーゲストの思考がおかしな方向に転がっていく。
バーゲストは無意識のうちに特異点の影響を受けていたのだ。
すなわち、人種的に黒人などに身体能力が平均して劣っている日本人を蔑む思考である。
バーゲストは自分が愛するマスターへと、『立香は愛しているが体つきはみっともない』という評価をしていることになんの疑問も覚えていなかった。
立香だって内面を評価しなければ、あのションベンを漏らして立ち去っていったナンパ男と同じぐらいの魅力でしかないと、この特異点の影響で考えるようになってしまったのである。
「マ、マスター、それにしても一人なのですか? ランサーのアーサー王やライコウ、マルタ辺りと行動していると思っていたのですが……」
だが、一方でナンパを撃退したことで冷静さを取り戻したのだろう。
今身に纏っている恥ずかしすぎる水着が生み出す羞恥にも少し慣れてきたところで、立香が一人でいる理由が気になってきた。
なにせ、立香はモテる。
ハーレムの主なのだ。
任務に取り組むことよりも遊び呆けることを好むカイニスとモードレッド、あとはその時の気分によっては虞美人も含まれるが、そういった『ノリが軽い』サーヴァントならば立香から離れていることはおかしくない。
だか、マスターの母を自称する過保護な頼光や、槍を立香に捧げたと公言して憚らないランサーのアルトリアに、世話焼きで使命感の強いマルタのようなものが、揃ってマスターと別行動しているというのは非常に珍しいことと言えた。
立香はいつもの笑みを浮かべて、少し困ったようにポリポリと頬を指でかきながら応えていく。
「あ~、うん。なんかここではタイミングが合わなくて……ひょっとして避けられてるのかな?
俺ってなんだかんだで普通のやつだし、頼光さんたちではないけど、みんなにはみんなの関係ってのがあるしね。ブーディカさんとかは生前に旦那さんも居たわけだし。嫌いになったっていうと大げさだけど、ちょっと距離を取られても仕方ないことを無自覚にしちゃってたのかもね」
「ハハハ。面白いことを言うものですね、マスター」
立香がうっすらと不安に思っていたことを吐露していくと、しかし、バーゲストはそれを冗談と認識したように笑ってみせた。
「マスター、私はもちろんのこと多くの女があなたを慕っています。そう、あなたは一夫一妻という概念からは最も遠い、あなたを優先したポリアモリーな関係を皆が受け入れていますよ。あなたが他の女たちと愛し合っていることに嫉妬するのではなく、むしろ、私でも認めざるを得ないような英雄からさえも強烈な愛情を向けられていることに誇らしさを覚えるほどです。
多くのサーヴァントがそのはずですよ。どうぞ胸を張って、我らを侍らせるハーレムの主に相応しいのだという自信を持ってください」
「あ、あはは……そう、かな。ありがとう、バーゲスト」
バーゲストの言葉に、立香の体が震える。
あまりにも立香に都合が良すぎる言葉だからだ。
ポリアモリー、言うならば、閉じた関係性ではなく広がっていく関係性を築いている立香にとって、『私だけを愛してくれ!』と主張されることは、卑怯ではあるが避けてもらいたかった。
多くの女性と繋がりあい、多くの女性と愛を育みたいというのが立香の本音なのである。
その本音を全肯定してくれるようなバーゲストの言葉に、立香は顔がニヤついてブサイクな顔になってしまうのを止めることが出来ない。
だが、藤丸立香にとことん都合のいい女であるバーゲストの都合のいい言葉は止まらない。
「このバディ・リング、あなたの愛を感じて常につけています。あのバレンタインデーの想い出を、私は一生忘れることが出来ないでしょうね。マスター、あなたがどう思うと……私は、あなたを愛していますよ」
うっとりとした表情で自分の左手薬指につけたシルバーのバディ・リングを指でなぞる。
それはバレンタインデーに送ったチョコのお返しとして立香から与えられた、コマンドコードを指輪の形にしたものだ。
二人の間の愛の証なのだと思うとバーゲストは昂ぶる感情が我慢できなくなる。
そこでようやく、立香が自分の体を欲望に満ちた視線を向けている事に気づいたバーゲストの体に火がついた。
なぜだか他のサーヴァントが纏わりついていない今は、バーゲストにとって大チャンスだということに気づいたのである。
「そ、その、よければこの後にホテルに戻りませんか? あなたが不安に思っているというのならば、それが杞憂だということをたっぷりと教えてあげますので……❤」
「ッ! わ、わかった……ほ、ホテルに戻ったら、ね……うん、うん! よろしくね、バーゲスト!」
二人は向かい合って笑い合う。
立香は首を大きく上に傾けて、バーゲストは首を大きく下へと傾けた、身長差カップルとして当然の姿勢となるのだ。
あまりにも不釣り合いだ。
バーゲストという強さと美しさを見事に同居させた絶世の美女のパートナーとして、いくら藤丸立香が人類最後のマスターという険しい道程を踏破してきたとは言え、バーゲストのような女を侍らせるに足る男ではない。
もっと、バーゲストすら上回る立派な体躯と、あの見るだけではっきりとセックスに貪欲だとわかる性欲を満たしてやれる、強い男でないといけないのだ。
『そう、アレはオレのモノだナ……!』
その条件にピタリと合ってしまう、とある黒人がニヤリと笑う。
バーゲストに狙いを定めたその黒人は、長い脚を大きく動かして、二人へと近づいていく。
そう。
源頼光を堕としたジョン・スミスのように。
アルトリア・ペンドラゴンを堕としたトロイのように。
虞美人を堕としたカーティスのように。
カイニスとモードレッドを堕としたテリー・ロッドのように。
マルタを堕としたドミニクのように。
この黒人がバーゲストを堕とすという未来が確定してしまった瞬間である。
『Hey! キミたちがカルデアのマスターとサーヴァントだナ?』
弾んだ声と同時に、立香とバーゲストが振り返る。
その振り返る瞬間に、バーゲストの引き締まった体にはあまりにも不釣り合いな爆乳が『ぶるるん❤』と卑猥に揺れて、その黒人は顔がニヤつくのを止められなかった。
そのまま黒人が手を上げると、ゆらりとした様子で空間が歪んでいく。
この現象を、立香とバーゲストは知っている。
「聖杯っ!?」
「貴様、何者だ!」
それは特異点を創り上げている性位牌が、世界の中から浮かび上がる瞬間の世界の歪みが可視化されたものなのだ。
この男が、聖杯の所有者――――つまりは、特異点を創り上げた黒幕ということだ。
立香は緊張感の孕んだ顔になり、バーゲストは『ビーチデート』ということで、お腹を見せて甘える大型犬のようにトロトロに蕩けていたのだが一転して女英雄としての顔に切り替わった。
歯を剥き出すような獰猛な顔つきとなり、聖杯を所有しているということで不意打ちを行った場合のリスクを考えて攻撃を行っていないだけで、倒せると確信をすれば今にも殺してしまいそうな、そんな恐ろしい気配を放っている。
『オレは今はオレが持ってルんダ。これが欲しけレバ……カルデアのマスター!』
そんな向かい合うだけでも怖気づいて、気の弱いものならば失禁してしまいそうなバーゲストを前にして、その黒人――『サイモン』はニヤニヤとした不快感を煽る笑みを浮かべたまま、大きく言い放った。
『お前がオレと、勝負をするンダ!』
これこそが、カルデアが決定的に破滅してしまう出来の悪い茶番劇、その幕開けなのだった――――。
◆
(このサイモンという男……何を考えているんだ?)
バーゲストは隣に並んだ男へちらりと視線を動かし、サイモンという黒人を観察する。
見たところ、自身が仕える妖精女王モルガンが常から放っている恐ろしい魔力や、そのモルガンに比肩すると言われるようなトップサーヴァントたちが持つ、わかりやすい強さというものは持っていない。
そういった、魔力というものにだけ注視するならば、サイモンは普通の男に過ぎないだろう。
だが、そんな一般人にしか見えないからこそバーゲストの中で警戒心がどんどんと膨らんでいくのだ。
無意識に思考の中でも、最も頼りになる騎士としての己が出てしまうほどに、サイモンという黒人
(このサイモン、只者ではない……! 剣を交えれば私が勝つだろうが、それでも計り知れない、未知数の恐ろしさを感じる……!
体格で言えば私を上回る身長と身体の厚み、ビーチには不釣り合いなタンクトップから覗ける腕は幾重にも重なった綱のようだし、やはりこの場に不釣り合いなデニムジーンズは今にもはち切れそうなばかりに太い足がねじ込まれている……!
英霊ほどの力があるかはわからないが、少なくともマスターのような貧弱な日本人は、それこそ赤子の手をひねるように簡単に制圧されてしまうだろう。それこそ、私が今まで経験してきた男たちに並ぶほどの猛者だ。マスターのためにも、私が常にサイモンを観察して警戒しておかねば……!)
バーゲストはジロジロとサイモンを見ていく。
サイモンは恵まれた体格をした巨漢であった。
190センチの長身であるバーゲストよりも視線が高い位置にあるほどの身長と、はちきれんばかりにパンパンに膨らんだ胸板と太すぎる両腕。それでいて、バーゲストのように鍛えられた腹筋は余分な脂肪が一切として存在しておらず、大きすぎる肩幅と胸板によって『逆三角形』が見事に作られている。
黒黒とした肌もまたその強靭な筋肉によく似合っており、この砂浜を照らす燦々とした太陽を反射するように肌自体が光っているようだった。
それはバーゲストが、『自分よりも優れた強さを持っている』と感じて恋をして愛を語り合い――最終的に、捕食していってしまった恋人妖精たちに良く似ている特徴だった。
マスターやアドニスが例外なのだ。
バーゲストの本来の性的な趣向は、とにかく『強い者』であり、そういう意味ではひとめで雄的な強者であるとわかるサイモンは、バーゲストの好みのど真ん中であった。
(そ、それに……体つきで誤魔化されていましたが、顔立ちもかなりキュートではないですか……? それこそ、年齢はマスターと変わりがない程度の、少年から大人に移り変わろうとしている頃では……? 甘いマスクのガウェイン卿をさらに幼くして黒人になったような……王子様的な筋肉イケメン……! ま、まずいですねっ……私のタイプそのものです!)
バーゲストの好みであるかどうかという点で言えば、顔立ちについてもまさしく好みだった。
立香やアドニスで新たに生まれた、庇護欲をそそる麗しい顔立ちの美少年という性癖の観点から見ても、サイモンはかなり整った甘いマスクをしている。
それこそ、バーゲストが敬意を向けている汎人類史における円卓の騎士、太陽の騎士ガウェイン卿のような、バーゲストも感心する見事な筋肉美と、王子様そのもののと言った甘いマスクのギャップをサイモンが持っていたのだ。
様々な男に抱いた恋心を一つにしたような理想に、バーゲストは知らず知らずに胸が高鳴ってしまう。
(いけません! わ、私はこれから、マスターとサイモンの勝負を決定づける重要な役割を果たすのですから……! このような動揺をしていては、カルデアの一員として聖杯を回収する任務を果たすことが出来ない! しっかりしなさい、バーゲスト!)
バーゲストは湧き上がってくるそのトキメキを必死に抑えていく。
サイモンがカルデアの協力者であったのならば、のん気に『あ~ん❤ マスターとサイモン、どちらも好みの男性が過ぎますっ❤ 私はどちらを選べば……い、いえ、マスターも多くの女性と結ばれているのですから、私もマスターとサイモンの両者と結ばれるのが、ポリアモリー的なのでは……❤』と、頭にお花畑が咲いているような馬鹿らしい思考に浸れたであろう。
だが、サイモンはカルデアの敵なのだ。
そんな男に懸想していいわけがない、真面目なバーゲストはその程度の分別はあった。
(しかし、敵ながら一騎打ちを申し出るとは天晴ですね。やはり、その恵まれた体躯から生まれる過信……いや、自信でしょうか。自惚れただけの男ならば、もっと卑劣な方法を取るでしょう。恐らく、価値観の違いから生まれるギャップ。最初はぎょっとし怒りも覚えましたが、サイモンにとってはそれが普通の手段なのでしょう)
それでも、チラチラと眺めながら隣だって歩くだけでサイモンへと好意的な思考が浮かび上がってきていることに、バーゲストは気づいていなかった。
ここで、立香がデートを楽しむために、バーゲストへと『今回の敵は女性をレイプしている卑劣な集団なんだ……!』という情報を先に与えなかったことが響いてきている。
バーゲストほどの誇り高い騎士ならばそのような蛮行は絶対に許さないため、それを知っていればサイモンに対する好感度は底を打った状態から始まっただろうから、このようにチラチラと物欲しそうな目でサイモンの素晴らしい筋肉美と甘い美貌を見つめて胸を高鳴らせるようなこともなかっただろう。
そんなサイモンの雄としての魅力を感じながら、バーゲストはサイモンが提案した『勝負の内容』を思い出していく。
(し、しかし……せ、『セックス勝負』を申し出てくるとは……! 勝負を申し出るときも、マスターしか見ておらず私に下卑た視線を向けていませんでしたし……彼にとっては、セックスはそういうものなのでしょうか……? あくまでスポーティーな、愛を伝え合う行為とは別種のエンターテイメントという文化で生きてきたという可能性はありますよね……もしも、私からマスターを奪う下衆な考えがあるなら、私の身体を不快な目で見てくるでしょうが、その気配は一切ありません。紳士そのものの態度です)
そう、サイモンが提案した勝負の内容は『セックス勝負』であった。
(しかし、私がそのセックス勝負の審査員になるなんて……マ、マスターの前でマスター以外の男に抱かれることになるとはっ……だけど、マスターが承知した以上は従う他ありませんね。だから、仕方ありません。仕方ないのです。この見るからに逞しくてかっこいい、私の理想の王子様のようなサイモンに、その体つきから想像できる、マスターとは比べ物にならない精力をぶつけられることは、仕方のないことなのですっ!)
それも、そのセックス勝負として抱く女はバーゲストになったのだ。
立香とサイモンはバーゲストとセックスをする。
その結果、バーゲストがマスターのほうが良かったと藤丸立香を選べば聖杯は回収されてこの特異点の問題は解決する。
逆に、バーゲストが黒人男性のほうが良かったとサイモンを選べば『人類最後のマスター』はこの特異点を解消することを諦めて、サイモンとその仲間たちが聖杯を所有し続ける。
立香とサイモンの一騎打ちを、サイモンは提案したのだ。
最初はバーゲストが断ろうとしたが、しかし、立香はそれを瞬きをするほどの時間もなく簡単に受け入れたのである。
さすがにそれはどうなのかと、バーゲストが恐る恐るといった様子で立香へ考え直さないかと提案するのだが、立香はバーゲストが愛してやまない輝くような笑顔を浮かべて、こう言ったのだ。
『バーゲストならいつも俺とのセックスで気持ちよくなってくれてるもんね。それに、気高い妖精騎士のバーゲストなら、あんな誰ともわからない男のセックスで気持ちよくなる』
―――そんな風に、バーゲストへと絶対の信頼を、盲目的に向けてきたのである。
(あなたはそれでいいかもしれませんが、私のプレッシャーは物凄いですよ! だ、だいたいマスターとのセックスは『幸せ』なのであって、『気持ちいい』わけではありませんっ! 肉体的な快感ではなく精神的な快感が大きいだけなのです! こ、このサイモンがセックスに長けた男ならば私だって……い、いやっ! なにを弱きになっているバーゲスト! お前はマスターのサーヴァントで、騎士で、恋人であろうが! どれほどサイモンという男が魅力的であろうとも、お前が今、真に愛している男は藤丸立香のはずだ! サイモンなどという男のチンポなど鼻で笑って、その自慢の締まりの良いマンコでねじ切ってしまえばいいのだ!)
セックスがド下手で男性器がひどく粗末なくせに、何故か自身のことを精力旺盛なヤリチンだと自惚れている立香に一瞬ではあるが怒りを覚えたが、バーゲストはすぐに自分を戒めた。
マスターを愛しているのは確かなのだから、新たに現れたサイモンがどれだけ魅力的な男であろうともバーゲストが愛するべきは立香なのである。
ならば、この勝負の結果はわかりきっているはうzだ。
このサイモンという男はよほどの自信があるようだが、立香が自信満々のようにバーゲストが愛を理由にして立香を選べば、誰も傷つくことなく、苦戦することすらなく、この特異点は解決されてしまうのだ。
ならば、そのセックス勝負に同意した立香の判断は優れていると言えるのかもしれない。
『安心しろヨ、バーゲスト。本当の男ってヤツを、オレがたっぷりト教えてやるカラナ』
「あんっ❤」
「お、おいっ! なにをしてるんだ!」
『すぐニ勝負が出来るようニ、今のうちから気持ちよくしてやるダケダ。ほら、人類最後のマスターくんモ、この女を愛撫したらどうダ?』
だが、そのセックス勝負の審査員となってしまったバーゲストはサイモンという魅力的な黒人男性によって翻弄されきっていた。
今だってそうだ。
サイモンがその甘いイケメンフェイスにニヤリと笑みの表情を浮かべながら、バーゲストの大きな手よりも大きな手のひらで『むぎゅぅっ❤』と握り潰してきたのだ。
それに対して立香が非難の声を上げるが、サイモンは子犬が吠えてきたなと言わんばかりの余裕たっぷりの表情で、『セックス勝負のタメの準備ダロ? 何を本気になっているンダ?』と鼻で笑ってみせる。
(なんて、大きな手❤ それに、この力強さもたまらない❤ 私の無駄に大きな乳房が、マスターも大好きな規格外の巨乳を握りつぶさんばかりに握ってくるなんて❤ あぁ、心地よい❤ 私がより強い力に支配されていくこの甘美な感覚は、マスターに召喚されてからは味わえなかったものです❤)
鼻息を荒くして起こっている立香とは対象的に、バーゲスト本人はその力強い乳揉み愛撫で確かに快感を覚えていた。
サイズが少々合っていない水着越しに爆乳を揉みしだいていくことで、どんどんと水着がズレていく。
だが、皮肉にも乳揉み愛撫で高まった快感によって勃起してしまった乳首が引っかかってその水着がズレて爆乳おっぱいが丸出しになることはなかった。
そんな快感を覚えているバーゲストを見て、立香もまた動き出していく。
「な、なら俺はこっちを愛撫するからね、バーゲスト!」
「へ……うん……?」
小さな手の短い指で、立香はバーゲストの水着越しにオマンコを刺激していく。
それを受けて、バーゲストの身体と理性に変化が起こる。
ただ、それはいい方向の変化ではなく、むしろ悪い方向の変化であった。
(…………水をさされましたね。なんですか、このみっともない愛撫は。そんな細い指でコスコスと擦られても気持ちいいわけがないじゃないですか。そもそも、私の淫らなマンコの肉でぷっくらと膨らんでいるオマンコじゃ、そんな弱々しい力と細い指では大した刺激にもなりませんよ。はぁ……本当に、マスターはセックスが下手ですね。おかげで、少し冷静になれましたが)
マスターのドヘタで情けない愛撫によって、高まっていた性感が一気に落ち着いていく。
バーゲストは覚めた目で、自分よりも頭一つ小さな身体の情けない日本人男性を見つめる。
そんな風に見下されていることにも気づかずに、立香は鼻息を荒くして大して気持ちよくもない愛撫を行っていくではないか。
なんと情けなく、惨めな姿だろうか。
『ククク……さ、さすが、人類最後のマスター、ダナ。こんな方法デ、オレの邪魔をするナンテ……クハハ!』
「お、俺だってバーゲストを気持ちよく出来るんだ! お前だけに有利に進ませないぞ!」
(違います、マスター。あなたは笑われているんです。未熟な愛撫で私の頭を冷ますことで、逆にサイモンの愛撫の効果も減らすという、奇跡的にいい方向に転がっただけのみっともない愛撫を、笑われてるのです。そんなことにも、気づかないのですね……)
それを互角に戦えていると感じているのは、立香だけだ。
どんどんとバーゲストの心は凪いでいく。
立香の生まれ故郷である日本には、『百年の恋も冷める』という言葉があるが、バーゲストにとってはまさしくそのような気持ちにもなった。
それでも、恋人に対して深い愛情を注ぐバーゲストのような愛情深い女は、立香を見捨てるような気持ちにまではならないのだが。
『ホラ、ついたゼ。ここが俺たちのアジトに使っテルBeach Houseだ』
そんな勝負にもなっていないセクハラの攻防戦を繰り広げていくと、サイモンが用意していると言った勝負の場所となるビーチ・ハウスまでたどり着いた。
黒塗りにされた威圧的なビーチハウスであり、ドアプレートとして黒いスペードの中心にアルファベットの『Q』の文字が白く染め抜かれているものがかかっていた。
そのドアプレートを見て、立香は既視感を覚える。
「…………あれ? このマーク、どこかで……?」
ここで気づけていればまだ未来は違ったのかもしれない。
だが、立香は気づけなかった。
まだ再会できていないアルトリアはともかく、頼光と虞美人、カイニスとモードレッド、そして、マルタがこの特異点に着てから身に付けだしたアクセサリ、『QoS』ブランドと同じマークであることに、気づけなかったのだ。
サイモンがニヤニヤとした顔のままそのドアを開くと、むわぁっとした淫猥な空気が漂ってきた。
「うぅ……これは……❤ 性の、臭いだな……❤ 女は居ないのにこれほどとは、どれだけの男と女がこの場でまぐわったのだ、全く……もはや、このビーチハウス自体に卑猥なセックスの臭いが染み付いているではないか❤」
(やはり、常習的にセックスをする文化を持つコミュニティということか……❤ 私が考える貞操観念とは違うものがあるため、セックス勝負などという奇妙な勝負を挑んできたとわかるな……❤)
人間とは異なった感覚を持つバーゲストは嗅覚にも秀でているため、その淫猥な空気の正体にも簡単に気付くことが出来た。
恐らく、バーゲストと立香を待ち構えていたのだろう。
中には複数人の黒人たちだけが居て、常に侍らしている女たちの姿は見えなかった。
それでも、セックスの臭いがバーゲストには感じ取れてしまう。
これはセックスにセックスを重ねて、ついには建物自体にセックスで生じる臭いが染み付いてしまったからこそ放ってしまう臭いである。
「くんっ❤ くんくんっ❤ すぅぅぅ~~……はぁぁぁ~~………❤」
そして、そのセックスの匂いはバーゲストにとっては甘美な罠となっていた。
弱々しい雄である立香との、心だけは満たされるものの身体は満たされない不完全燃焼セックスしかしてこなかったカルデア生活では絶対に味わえない、雄の精の臭いが充満しているのだ。
バーゲストはまさしく犬のように鼻をヒクヒクと鳴らしてその臭いを堪能してしまっていた。
『HuHuHu……』
『HAHAHA……』
『こっちダ……! Fight Clubだゼ!』
そんなバーゲストのはしたない様子と、弱々しい雄である立香を見下すような笑いがビーチハウスの中に充満していく。
立香はむっと顔をしかめたが、精の臭いに夢中になっているバーゲストは気付くことが出来ない。
そんな二人はサイモンに導かれて特別個室へと案内される。
セックスのための勝負の場には、大きなベッドが一つとひとりがけの椅子と大きなソファーの三つの家具だけが残されている、なんとも簡易的な空間だった。
『サア、勝負ダ。人類最後のマスター、その腕前……いや、Cock(男性器)の力、見せテもらおうカ!』
「い、いいよ! やってやる! まずは……セックスだけじゃなくて、バーゲストの愛撫に耐えられるかで勝負だ! それで良いな!?」
『良いゼ。射精を我慢できたほうがOne Pointを取るってことダナ。じゃあ、次は『Sex』での勝負ダナ。最後の三本目は、この女が男を気持ちよくする方法を選ぶ、『FreeStyle』と行こうカ』
「え、さ、三回も射精するかもしれないの……? い、いや! やってやる! 二回勝てばいいんだしな!」
勝負の方式は三本勝負の二本先取した方が勝利という形式になった。
一本目はバーゲストによる手コキ。
二本目はバーゲストとのセックス。
そこでも勝負が決まらなかった場合の三本目は、バーゲストがとにかく男を早く射精させられる方法を取って奉仕をするということになった。
だが、立香は場合によっては三回も射精することに怖気づいてしまう。
連射性能が著しく低い立香は、バーゲストとのような激しいセックスならば、一度射精しただけ失神するように眠っているのが常なのに、三回も連続射精できるとは到底思えなかったのだ。
それでもここで怖気づいては行けないと自分を奮い立たせて、キリリッと大して迫力のない顔でサイモンを見上げるようににらみつけるのだった。
「そ、それでは、私はこの椅子に座りますので……二人は両側に立ってください。そこで同時に手コキをして、先に射精をしたほうが負けです。いいですね?」
「いいよ! バーゲスト、よろしく!」
ぽろり、と。
立香がズボンを脱ぎ捨てると、そんな擬音が聞こえてきそうなほどの弱々しい勢いで粗末なチンポが露出されてしまった。
それを見て、バーゲストは少しだけ安心をした。
(ふふふっ……❤ 相変わらず、マスターのオチンポは愛らしいですね❤ みっともなくて物足りないのは事実ですが、これを見ていると非常に落ち着きます……❤ マスターへの愛情が蘇るといいましょうか……ああ、これで大丈夫❤ 私はマスターへの愛撫を程々にして、このサイモンへと本気の手コキですぐさま射精へと導くことが出来るでしょう❤)
先ほどの情けない愛撫で弱まりかけていた立香に対する愛情が復活していく。
バーゲストは気持ちを入れ替えて、カルデアのために人理のために、このセックス勝負で立香を勝たせてみせると言わんばかりの引き締まった表情を作り、サイモンを睨みつけていくのだった。
『Ok! さあ……頼むゼ!』
「………………え? ふぎゅぅっ❤❤」
「ナ、で、デカい……なんだ、それ……出した瞬間に、少し離れてたバーゲストの頬を叩くぐらいの大きさだなんて……」
ぼろん、と。
立香がズボンを抜いた時とは比べ物にならない勢いで黒人特有の大きなチンポが露出されていく。
その大きさはと言えば、バーゲストとの距離は立香と同じぐらいの距離だったというのに、その長すぎるチンポでバーゲストの頬へとチンポビンタをしてしまったほどの大きさである。
バーゲストは、打たれた頬に熱が集まってくるのを感じていた。
(でっっっっっっっっかぁぁぁっ❤❤❤❤ な、なんですか、この巨根は❤ 立香はもちろんのこと、今までの男とさえ比べ物にならないほどの大きさではありませんか❤ こ、こんなもの知らない❤ こんなに力強くて、大きくて、かっこいいオチンポは知りません❤❤❤❤)
バーゲストは、その大きなチンポに心を奪われた。
まさしく『Big Black Cock(黒い大きな男性器)』と呼ぶに相応しい巨根であった。
それこそ、マスターのような雑魚チンが相手でなくとも、バーゲストが今まで身体を共にしてきていた男たちと比べても大きなものだ。
なにせ、そのCockは全長31.5センチ、太さは円周22.3センチで、直径は約7センチと言ったところだろう。カリの高さに関しては1.6センチほどであろうか。
「すんすんっ❤ すんすんっ❤ すんっ❤ すぅぅぅぅぅぅっ❤ はぁぁぁぁぁっ❤」
「バ、バーゲスト……?」
「すうぅぅぅ……はっ!? い、いえ、なんでもありません! あ、あなた、臭いのではないですか!? こ、こんなものを私に握らせたり、膣に挿入するつもりですか!」
そんな規格外の巨根で頬を打たれて目の前に突きつけられたバーゲストが取った行動は、なんともはしたないものだった。
顎を上げて鼻をチンポに近づけてスンスンと物凄い勢いで臭いをかぎだしたのだ。
ブラックドッグの名の通り、犬にも近しい特徴を持つ妖精であるバーゲストの本能がさせるのだろう。
恍惚とした表情でBig Black Cockの臭いを嗅ぎ続ける様子を見た立香が、呆然とした表情でバーゲストの名前を読んでようやく意識を取り戻し、言い訳をするように言葉を早口で並べ立てていくのだった。
『HAHAHA , Sorry! まあ許してくれよ、バーゲスト』
「あぅ……❤ あ、頭を、撫でるなぁ……❤」
だが、そんな取ってつけたような敵対心も、バーゲストのさわり心地の良い美しい髪をサイモンが乱暴にぐしゃぐしゃと、それこそ飼い犬を褒めるように撫でてやると、途端にトロンとした顔に蕩けてしまう。
立香が一度も見たことのない表情だ。
この時点で立香の胸中に不安がよぎるが、すぐにその考えを切り捨てる。
『きれいなHairダナ。触ってるダケで、指が気持ちよくなるゼ』
「はぅ、ふぅぅっ……くぅぅぅ~~んっ❤」
(バ、バーゲストはサイモンを油断させているんだ! 少しでも早く射精するように、心を押し殺してサイモンに媚びているんだな……! くっ、俺が頼りないからバーゲストにこんなことをさせるなんて……絶対に勝ってみせる!)
「さあ、勝負だ! 頼むよ、バーゲスト!」
なんとも見事なポジティブシンキングであろうか。
誰がどう見てもサイモンの魅力にメロメロになっている大型犬系女子のバーゲストなのに、それを演技だと思い込もうとしているのである。
そして、その小指ほどの大きさしかないチンポを突きつけるように腰を前に出していく。
「へ、あ、ああ……そう、ですね。さあ、勝負を開始します。行きますよ……!」
バーゲストはその立香の情けなさ過ぎるPenisを見て、次にサイモンの逞しすぎるCockを見つめて、冷静さを取り戻した。
その代わりに、あまりにも情けない立香へと抱いていた愛情がぐぐぐっとものすごい勢いで下落していったのだが、しかし、バーゲストの理性を取り戻せたのだから構わないだろう。
「あぁ、あぁぁっ!? き、気持ちいい、気持ちいいよ、バーゲスト!」
『Oh,Good! これは想像以上ダネ……!』
シコシコっ、シコシコっ、シコシコっ。
バーゲストは平等にチンポをシゴきあげていく――こともなく、はっきりとその熱意の差が伝わるほど、手コキのテクニックに違いがあった。
立香のPenisに対しては親指と人差し指で丸を作ってその丸を上下にシコシコと動かすだけの、あまりにもおざなりな手コキである。
一方で、サイモンのCockに対しては五本の指全てを使って、その時々にどの指に力を込められているのかも変わるような、そんな男性に対して強烈な快感が生じる見事な手コキを行っていくのだった。
これは立香を愛しているため、立香に勝利を捧げようとわざと立香への快感を弱くしてサイモンを責め立てているというわけではない。
むしろ、感情の面ではその逆と言えた。
「ふぅぅぅぅっ❤ ふぅぅっぅ~~❤」
(なんてっ❤ なんて手コキのやりがいがある素晴らしいチンポでしょうかっ❤ 私が力を入れても折れる気配がない、まるで中に鉄杭でも仕込んでいるのかと思えるほどの硬さっ❤ 私の五本の指で握ってもまだまだあまりのある、逞しすぎる長さっ❤ あぁっ❤ 私がチンポで遊んでも充分に耐えられる持久力もたまりませんっ❤ マスターに同じことをしようと思えば数秒で射精……いえ、私の力でチンポを再起不能になる形で握り潰してしまいますからね、このような楽しい手コキは本当に嬉しいですね❤)
そう、バーゲストの根っこにある淫乱という『性質』が湧き上がってきたのだ。
立香のような情けない雑魚雄相手にセックスを楽しむことなど出来るわけがない。
例えば、バーゲスト自身が考えたように、今サイモンへと行っている手コキを立香に行えば、立香は十秒と持たずに射精をしてしまい、場合によってはそのままバーゲストの凄まじい握力で潰されてしまうことも考えられるだろう。
だが、サイモンは違う。
バーゲストが思わず力を入れてしまってもまるで気にせず、鼻歌を行いながらその手コキを味わっているではないか。
『Nice technic! これはいいネ、マスターはいつもこれを味わっているんダナ』
「あぁ、あぁぁっ!? バーゲスト、気持ちいい、も、もっと弱めて、弱めてぇぇ!」
「はぁぁっ❤ はぁぁぁぁ❤ 硬い、長い、臭いぃ……❤ これ、すごいっ❤ 手コキしてるだけなのに、興奮してしまうっ❤」
余裕綽々といったサイモンに比べて、立香はただ親指と人差し指で輪っかを作って上下に擦られているだけなのに限界を迎えつつある。
そこで情けを乞うようにバーゲストへと手加減をねだるのだが、サイモンの逞しすぎるBig Black Cockに夢中になっているバーゲストは立香の声すら届いていなかった。
(かっこよすぎるっ❤ やはり男はチンポの見事さも魅力に繋がりますね……❤ さあ、マスター❤ あなたでもこのおざなりすぎる、輪っかを作って上下にするだけの手コキなら耐えられるでしょう❤ 私はその間に、サイモンへと全力で手コキを行って楽しみ、い、いえ、射精をさせてみせますので、どうぞ耐えて―――❤)
「あぁっ、もう射精るっ! 射精るぅぅっっ!?」
「……………え?」
だから、バーゲストは気づかなかった。
いつもなら『し~~こ、し~~~こ❤』という、まるで子供をあやすために身体をゆっくりとぽんぽん叩くようなスローなリズムで行う手コキが、サイモンのチンポをシゴく興奮につられてしまい『シコシコっ❤ シコシコっ❤ シコシコっ❤』という、普通の手コキの速度よりも少し早くて激しいものになってしまっていることに、気づけなかったのだ。
そんな『普通の刺激』に、精力に関しては底辺を這いつくばる雑魚雄の立香が耐えられるわけもなかったのである。
立香はか細い雄叫びをあげながら、ついに射精してしまった。
「うわぁぁぁぁっ!?」
ぴゅるるっ、ぴゅっ、ぴゅぅぅ~~……!
「………………はい?」
バーゲストは理解できなかった。
自身が作った輪っかの中から水のように薄い精液が飛び出し、その輪っかの中からしなしなと萎びれていった立香のPenisが引き抜かれていく。
射精の快感による疲労なのか、ぺたりと床に尻餅をついた立香を見てもまだ理解が出来ない。
弱すぎる。
時間にして十分も経っていないし、そもそも手コキだってテクニックと呼べるようなものを披露したわけでもないのに、なぜ射精をしているか理解が出来ないのだ。
『オレの勝ちダナ……Oh!? バーゲスト、何ヲ!?』
そして、サイモンのあざ笑う声が聞こえた瞬間、バーゲストの何かが弾けた。
尻餅をついて見上げてくる立香へと視線をそらすように顔をサイモンの方へと向き直り、そのままその可憐な唇で、なんとそのBig Black Cockに吸い付いたのである。
「んじゅるるぅぅぅっ❤ ちゅぅぅぅ、ちゅぽっ❤ じゅるるるぅ、れろれろぉぉぉっ❤」
フェラチオである。
手コキを耐える勝負であるはずなのに、サイモンは敵であるはずなのに、勝負はついたはずなのに。
様々な『そのはずなのに』という前提を無視して、バーゲストはものすごい勢いでしゃぶりついていったのである。
サイモンの真っ黒な肌をした股間に、もっとジャングルのように黒々と生い茂っている陰毛の中へとその高い鼻を構わずに突っ込んでいるぐらいの、『本気のフェラチオ』ではないか。
「れろれろぉぉっっ❤ ちゅぅ、ちゅぅぅぅぅ~~❤ じゅぼぼぼぉぉっ、ちゅるるるうぅぅ❤」
バーゲストの誇り高さを連想させる美貌が、見るも無惨に歪んでいく。
そのBig Black Cockをじぃっと見つめるために目は寄り目になっている。
フェラチオが激しすぎるのだから口呼吸ではなく鼻呼吸になったことでその高い鼻には抜けた陰毛が侵入していき鼻毛のように飛び出ていた。
極め付きに、あまりにもチンポに激しく吸い付いているため頬が引っ込んで唇をすぼめて突き出すような、無様な『ひょっとこ顔』を披露しているのである。
こんなものは、幾度となくセックスをしてきた立香であっても、いや、強靭で精力に自信があったかつての恋人たちであっても見たことがなかった。
『くぅぅっ! うおぉぉっ!?』
どびゅるるるっ! びゅるるるっ! ぶびゅるぅっ! どぶびゅううううぅぅぅっぅ!
「んっぅぅぅぅっ~~~~❤❤❤❤」
バーゲストの貪欲な性欲が前面に出たフェラチオは奇襲のように突如訪れたため、性豪である黒人男性のサイモンであっても思わず射精してしまうのだった。
喉に向かって激しい勢いで流し込まれた精液を、バーゲストは目を細めながら嬉しそうに喉を鳴らして嚥下していく。
普通の女性ならばむせ返って吐き出してしまうほどの勢いと、濃厚すぎるほどに濃厚なザーメンの臭いと粘度によって、射精されたザーメン全てを飲み込む『ごっくんフェラ』など出来なかったはずだ。
なのに、バーゲストはじゅるるると凄まじい音を立ててその流し込まれたザーメンを一滴もこぼさずに見事に飲み干してしまった。
「バ、バーゲスト……?」
自分に対しては絶対に見せないほどのひょっとこフェラで、ザーメンを完飲してしまった恋人の姿に呆然とした表情で立香はバーゲストの名を呼ぶしかなかった。
ただ、自分には見せなかったひょっとこフェラというが、立香のような可愛らしいpenisを持っている雑魚雄相手にこのようなハードフェラを行えば、間違いなく数秒で射精をしてしまうし、それどころかチンポが根本からボキリと抜け落ちてしまうかもしれない。
このようなハードフェラが生み出す強烈な快感を味わうためには、サイモンのような強靭でかっこいいCockでなければ、安全上味わうことが出来ないのだ。
「んぅぅ……ごくっ、ごっくんぅっ❤ ふぅぅ、はぁぁ……❤ こ、これで、良いですね❤ 手コキ勝負ではマスターが敗北しました❤ それは事実ですが、このままでは一度射精したマスターとムラムラとしたままのサイモンでは、次のセックス勝負で有利不利がはっきりしてしまいます❤ 後で何かを言い訳をされても困りますから、今のうちに……うぅぅ、んんぅう―――――❤」
そこから早口で言い立てられるバーゲストの、『なぜバーゲストは手コキ勝負が終わった後にフェラチオを行ったのか』という説明を聞いて、立香は先ほどの不安そうな顔を吹き飛ばす。
まるでサイモンに魅了されて、『立香の貧弱過ぎるpenisとは比べようもない、サイモンの立派過ぎるcockに奉仕をしたいのです❤』というマゾ牝が持つ奉仕欲求が爆発されたのかと思った。
だが、実際はバーゲストはその騎士道精神に基づいて、次の勝負が射精をしたことで立香が有利になってしまった状況を平等にしようとしただけだったのだ。
もちろん、そんな『言い訳』を信じているのは、情けないpenisを持っている愚鈍な立香ぐらいのもので、女というものの本性を知り尽くしている経験豊富なcockの持ち主であるサイモンはニヤニヤと笑っているのだが。
「バーゲスト、そういうことだったんだね! やっぱり平等で誇らしい騎士に相応しい、フェアプレー精神――――」
立香はバーゲストの騎士道精神に感動し、それを褒め称えようとする。
だが、その言葉を遮るように、胸を抑えたバーゲストの口から信じられない音と臭いが溢れ出しのである。
「んげぇ゛ぇ゛ぇ゛ぇ゛ぇ゛っ゛ぇ゛ぇ゛~゛~゛っ゛ぷ❤❤❤❤」
「うわぁ、く、くっさぁっ……!?」
ザーメンを一度に嚥下したバーゲストが、ゲップをしてしまったのである。
あの理想の騎士を形にし、鎧を脱げば貞淑な淑女そのもののバーゲストが下品の極みであるゲップをするなどと、目の当たりにしてもなお信じられないほどの衝撃的な攻撃だった。
しかも、その原因がフェラチオで射精させたザーメンを完飲したことが原因である。
「んぐぅぅっ❤ し、失礼しましたっ❤ マスターもサイモンも忘れてください❤」
「あっ、う、うん……」
『何がダ? 聞くことを忘れルようなことナンテ、何もなかったぜ? 素敵なLadyガ、オレのcockを気持ちよくシタ……それだけダロウ?』
「っ❤ さ、サイモン……❤」
そんなザーメンゲップをバーゲストも恥じらっているようで忘れてくれと言われ、立香はただただ動揺して、曖昧に頷くことしか出来なかった。
だが、サイモンは違う。
椅子に座っているバーゲストの髪を、先ほどもしたように優しく撫でてやりながら、ザーメンゲップの全てを当たり前のこととして受け入れつつ、恥じらっているその内容自体には触れないというヤリチン仕草を見せたのだ。
バーゲストは『ドキリ』と胸が高鳴り、さらに火がついたように頬を紅潮させてしまう。
事情を知らないものがこの瞬間だけを見れば、サイモンとバーゲストこそが恋人であり、立香はその間に入り込もうとしている下品な黄色い猿のように見えるほどに、二人だけの空気が一時的に作られてしまうほどだった。
「そ、それではっ❤ 次のセックス勝負へと参りましょうっ❤ それでは、敗者にハンデを与えるという意味で、先手はサイモンに❤ マスターはその愛らしいpenisを休ませてください❤ サイモンのcockは私がたっぷりと懲らしめておきますので❤」
「う、うんっ! わかったよ、バーゲスト!」
『HuHuHu……熱烈なお誘いダネ。バーゲストとのsex、楽しみダ』
だが、その奇妙な空気にバーゲスト自身も気づいたのか、慌てたように立ち上がって次の勝負に移ることを提案した。
その際に順番はサイモンを優先し、そこには理屈っぽい説明がされるものの、冷静な人物が見ればサイモンの立派なcockと早くセックスをしたい牝の姿であると見抜けただろう。
事実、冷静さを維持しているサイモンはそれを見抜きつつもニヤニヤと沈黙し、バーゲストの変調を感じ取りつつもそれを超えるエロさで興奮しきっている立香はまるで気づかない。
バーゲストは一足先にベッドに寝転がり、そのまま、紐ビキニを脱ぎ捨てていくのだった。
『Oh! なんてbustダ……! これほどの大きさハ、オレも見たことがないナ!』
「ぅっ~~~~❤❤❤❤ は、早く来なさいっ❤ 見世物ではないのですよ、サイモンっ❤ セックス勝負の開始ですっ❤」
『pussyも良いナ♪ このヌレヌレで光を反射する姿ガたまらないゼ♪』
その『どたぷん❤』という擬音が聞こえそうな勢いで、水着の中から弾けるように顔を出した爆乳を見て、経験豊富なヤリチン野郎であるサイモンであっても思わず感嘆の声を漏らしてしまった。
バーゲストはその言葉に照れたように喉を鳴らした後に、早くそのかっこいいcockを挿入しろと、一騎当千の剣を振るう手で『くぱぁ❤』とすでに濡れ濡れになっているオマンコを広げてみせる。
その濡れそぼったオマンコは、立香を初めとして多くの男とセックスをしてきたクセに、男を知らない乙女のようなキレイなオマンコだった。
それは、今までの男が本質的にバーゲストよりも弱い雄だったということを意味している。
バーゲストほどの強く美しい女を支配するという男の夢は、残念ながら今までの男では誰も叶えられなかった。
そのため、オマンコをヤリマンさながらの黒々としたものに変えることが出来なかったのである。
『それジャっ……挿レル、ぞ!』
「ふぎっぃっ❤ あ、熱いっ……❤」
サイモンのcock、その先端がピッタリとバーゲストのpussyに口づけをするように添えられる。
途端に、今まででも充分に流れ出していたはずの愛液がさらにドバドバと流れ落ちていく。
牝の本能が、サイモンこそが自分を支配するには十分な器を持った雄だと認めてしまったのだ。
それこそ、結局は弓をひくことになったとは言え、一度は忠義を誓ってカルデアに召喚されてもなお臣下であることを赦した偉大なる妖精女王モルガンほどの大器の持ち主だと、牝の本能が見抜いてしまったのである。
まずい、このままでは『堕ちて』しまう。
そして、それを悦んでいる自分が居ることに加えて、その姿をマスターに見られてしまう。
それを感じ取ったバーゲストは、セックス勝負の順番を入れ替えようと考えた。
今さら牝の本能がこの相性バッチリなBig Black Cockとセックスをしないなんて選択肢を取ることなど出来ないが、そこで晒す無様をマスターに見られるわけにはいけない。
さっさと射精させて、いつものように射精疲れの睡眠を取らせてないと、と考えたバーゲストが言葉を発しようとした、その瞬間だった。
「ま、待って、やっぱり先にマスターを――――」
『フンッ!』
「――――おっ❤」
ずぶぅぅ、ずぶずぶぅぅぅ、むにゅむにゅぅっぅぅ、ずぶりゅぅっぅぅっぅっぅ!!
「おぉぉっ❤ おほぉぉお、おぉぉおっ❤ おっほぉぉっっぉぉぉぉっぉっぉ~~~~❤❤❤❤」
バーゲストの言葉が言い終わる前に、サイモンは腰を強く突き出してBig Black Cockがバーゲストに挿入されてしまった。
死んでしまったのではないかとバーゲストが本気で感じるほどの、物凄い衝撃である。
身も心もバラバラに砕けてしまうような、いや、実際に心も砕けてしまったほどの衝撃だ。
捕食衝動――――それは愛すれば愛するほど、愛する者を取り込もうと捕食に顧みる、バーゲストという黒き災厄の拭いきれない悪癖だ。
それが吹き飛んだ。
妖精女王モルガンが『妖精騎士バーゲスト』という着名(ギフト)をつけることで抑え込んだその災厄の証を、まるで首輪に繋がれたリードを引いて犬を躾けるような手軽さで、サイモンはバーゲストの捕食衝動を挿入するだけで抑えつけたのである。
「ほごぉぉ、ぉぉぉっ❤ んほぉぉ~~……❤」
『Huh……少しゆるいな……? Hey! もう少し締め付けるンダ!』
「ふぎぃっぃぃぃぃぃぃぃ❤❤❤❤」
ガクリと、全身から力が抜けていく。
その鍛えられた肉体が何一つ意味をなさないほどに、指先一つも満足に動かすことが出来なかった。
そこを責め立てられるように、サイモンのcockがバーゲストの蜜壺の中を激しく前後していく。
ゴリゴリと、ギシギシと、バーゲストの膣壁が削られていく。
今までの経験から、男とは慣れるまで自分のpussyの中で抽挿を行うことも難しいぐらいには、自身の『締まり』はいいものだという自覚があったバーゲストにとって、この乱暴なピストン運動は初めての出来事だった。
「ほぉぉ、ぉぉっぉ❤ し、締めますっ❤ cockを気持ちよくするために、締めますっ❤ ふぅぅ、うぎゅぅぅぅっ❤ イグッ❤ まだセックスの途中なのに、イグうぅっぅっ❤」
『Yes! 調子が出てきたナ、バーゲスト! いい感じの締め付けだゾ!』
その激しいピストン運動は、バーゲストの身体から力が抜けていたから行えたのかというと、決してそういうわけではなかった。
ぎゅぅぅという音が聞こえそうなほどにマンコに力を入れて、まるで万力で締め付けるように激しくcockに刺激を与えるのだが、サイモンは気持ちよさそうに笑みを浮かべた後に変わらず力強く腰を動かしていくではないか。
これはバーゲストの知らないセックスであった。
愛多き女であるバーゲストは男を多く知っているつもりだったが、実際のところは、男のことなど何も知らないことを嫌でも思い知らされてしまう。
そうだ。
今までバーゲストが雄だと思っていた相手は、本物の雄ではなかったのだ。
牝である自分に捕食されてしまうような、手籠めにした女を支配できない貧弱な男は、本物の雄と呼ぶことなど出来るわけがない。
このように、自分を組み敷いて腰を振って、それだけで女を翻弄する男こそが本物の雄なのだ。
「バ、バーゲスト……?」
「マ、マスター……ふ、ふふふ、ふふふふふっ❤」
そんな『貧弱な男』の代表格である立香がポツリと言葉を漏らし、そこでやっとバーゲストは自分の恋人がこのセックスを見ていることに気づいた。
続いて、その情けないpenisが目に入る。
笑いが止まらなかった。
この雑魚雄は、自分の恋人が黒人男性様に抱かれている姿を見て――――勃起をしているのだ。
それもただの勃起ではなく、バーゲストとのセックスでも見せなかったほどの激しい勃起。
それでもサイモンのBig Black Cockの十分の一にも満たないような粗末な勃起であるが、それでもいつもの勃起よりもpenisを固く大きくしているのだ。
このような雑魚雄をなんというか、バーゲストはカルデアでの活動で知識として身に付けていた。
『寝取られマゾ性癖』、だ。
恋人を別のオスに奪われることに強い興奮を覚える、倒錯的なんて気取った言葉では説明できないほどにどうしようもない、最低最悪の雑魚雄だけが性癖である。
そう思うと、バーゲストは笑いが更に止まらなかった。
だが、その笑いがサイモンは気に入らなかったようである。
「おぉぉっ❤ ふ、深いっ❤ 一番深いところに、チンポが刺さるっ❤ 黒い剣で、子宮が貫かれてるうぅっ❤ おほぉぉ、ぉぉぉっ❤ 旗を立てられてるっ❤ この子宮はオレのものだと、占領した砦に旗を掲げるように、子宮が責められるぅぅぅっ❤」
『何を気にしてるンダ! お前は、オレと、sexをしているんダ! オレ以外のことは考えるナ!』
「はひぃぃぃぃぃ❤ ご、ごめんなさいっ❤ 無礼なこと、でした❤ しゅ、集中っ❤ 集中しますっ❤ あなたとの、サイモンとのセックスに集中しますぅぅっ❤」
即堕ちというのだろう。
元々、サイモンのたくましい肉体と堂々とした振る舞いに、女として『キュンキュンっ❤』と胸を高鳴らせていた恋多き女であるバーゲストが、そのcockによって子宮まで掌握されてしまったのだ。
そのcockが膣道を、入っては抜き入っては抜きと動いていく度にサイモンに対する恋慕が強まっていってしまう始末である。
これだけでもバーゲストはサイモンに夢中になるに十分な責めだというのに、『女を堕とす』ことに特化した生き物とも呼べるほどのヤリチンであるサイモンは、バーゲストを決定的に堕落させるために、さらに強烈な責めを行っていくのだ。
「んおぉぉっ❤ あ、脚を掴まれて、腰が上がって、ふぎぃぃぃっっ❤ こ、これぇぇ❤ 私がマスターにやってたの、私が逆にやられてるぅぅっっ❤ 腰が壊れるぐらい腰を撃ち落とされて、一番奥にガツンガツンって、おぉぉぉっ❤ 気持ちいいっ❤ 気持ちいいぃぃぃっぃっぃぃぃぃ❤」
サイモンはバーゲストの両足首をガッチリとホールドし、その太すぎる脚を大きく上げさせて、腰を大きく浮かせる姿勢をとらせる。
その浮き上がった腰を壊す勢いで、cockを前後というよりも上下に動かしていくのだ。
日本で言う『深山本手』という体位でバーゲストを責め立てていく。
「んおぉっっっぉぉ~~~~❤ 壊れるぅっ❤ 私の身体が壊れるっ❤ どんな戦いでも屈しなかったのに、このチンポで負けるっ❤ 凄い、凄すぎるっ❤ 勝てない、これに勝てないィィっ❤ もっともっと、責めてくれぇぇぇ❤」
その全てがバーゲストに効果的な責めだった。
捕食衝動というもの事態をねじ伏せるような力強さ――――これほどの強さを持つ雄に、牝であるお前が勝てるわけがないと言わんばかりに、バーゲストが受け止めきれないほどの快感が流されてくるのだ。
実際に、バーゲストはもはや媚びるように顔を緩めきっている。
美しさと強さを捨て去った、媚びと愛らしさだけが残るバーゲストに、サイモンは最後のトドメを指していく。
『射精するゾ! 全部受け止めロ! お前の子宮デ、オレの全てヲ受け止めロ!』
「ひぎぃぃぃぃぃっ❤ くるっ、くるぅぅぅっ❤ ザーメンが流し込まれてくるのぉぉっぉっ❤❤❤❤」
どびゅるるるぅ! びゅるるぅ! どぶぴゅうぅぅぅっ! ぶっぴゅびゅるるるぅぅぅぅぅ!
「お゛ほ゛ぉ゛ぉ゛ぉ゛ぉ゛っ゛っ゛ぉ゛っ゛ぉ゛っ゛ぉ゛ぉ゛ぉ゛っ゛ぉ゛❤❤❤❤」
注ぎ込まれてくる精液の勢いに、バーゲストの理性が流されていく。
今まで築き上げていたものが簡単に崩れ去っていき、新しい自分が生まれることに気付かされる。
あまりの快感に脳も体も受け止められず、ビクンビクンと激しく痙攣していくのだが、足首をガッチリとホールドされているためにベッドから落ちるようなことにはならなかった。
バーゲストほどの巨体の女性が痙攣しながら暴れているというのに、この拘束力はサイモンの力強さの現れであり、それを感じれば感じるほどにバーゲストという牝は再びサイモンという雄に夢中になっていってしまう。
「あ、あへ……あへぇぇっ……❤」
『Huh……最高だったゼ、バーゲスト』
その痙攣も治まったところで、長い射精を終えたサイモンがバーゲストの中からその巨大なcockを抜いていく。
黒々とした立派なcockがバーゲストの粘度と濃度の高い愛液でテラテラと淫靡に光っている。
それは同性である立香ですら思わず目を引かれるような、独特の怪しい魅力を放っていた。
「ふぅぅ、うぅぅ……す、素晴らしい、セックスでしたね……❤ 記録は、なるほど、この時間ですか……❤ この時間、マスターが私とセックスをして射精を耐えられば、二戦目はマスターの勝利ということですね……❤」
cockが引き抜かれたオマンコからはザーメンがこぼれ落ちることはなかった。
女性としては驚異的な腹筋を持つバーゲストが、その力の全てを利用してオマンコをきつく締めることでザーメンが外に出ることを拒んでいるのだ。
サーヴァントである以上孕むことなど出来ないというのに、サイモンという魅力的で優秀な男の子種を一滴残らず卵子で確保してみせるという、卑しい牝が持つ滑稽な習性の現れである。
「ああっ! 俺も頑張るからね、バーゲスト……!」
「……マスターと、これ以上の時間、を……」
時計をちらりと見て、サイモンとセックスを行っていた時間をチェックした後にバーゲストは立香を見つめる。
立香の顔ではなく股間に向いた視線とともに、カルデアの使命を重視するならば、立香と今以上の時間のセックスを行わなければいけない。
そう、あの素晴らしいcockを持ったサイモンのセックスの後に、あの情けないpenisを持った立香と、セックスをしなければいけないのだ。
「…………それでは、マスター。どうぞお入れください」
「わ、わかった……! それじゃ、行くからね……!」
ここが分岐点だったのだろう。
バーゲストは沈黙を続け、何かを決めたように顔を上げた後に、乱雑に足を開いていく。
立香はその様子に疑問を覚えることもなく、大量の射精をされたばかりなのに一滴たりともザーメンが流れ落ちることがないオマンコを注視している。
彼もまた、あの濃厚なセックスを見せつけられて興奮していたのだ。
一度射精すれば復活するまで幾らか時間のかかる立香なのだが、今回は僅かな時間を置いただけでその弱々しいpenisが弱々しい勃起をしているのだった。
その情けないpenisを、バーゲストのpussyへと挿入されていく。
「ふぅぅぅ……ふぅぅぅっ! あ、あれ、奥まで、くぅぅっ……!」
「…………」
にゅぷ、にゅぷぷ、ぐ、ぐぐぐ、ぐぅ~~……すぅん。
だが、その挿入が上手くいかない。
普段ならば膣襞が蠢いていき、まるで誘われるように立香のpenisが奥まで挿入されていくのだが、今回は膣肉がギチギチに閉まっており、短いpenisの途中までしか入らなかったのだ。
バーゲストはそんな立香の様子を、ひどく冷めた目で見つめている。
「な、なんで……! くぅっ、もっと奥までっ……ひぎぃ!? お、オマンコが動いて、き、気持ちいいっ!?」
「…………」
いつものように根本まで挿入しようと、もちろん根本まで挿入してもバーゲストの少し深めなオマンコの半分ほどしか到達しないのだが、立香はヘコヘコと腰を動かしていく。
だが、きつく締まったオマンコを割り行っていくほどの力が、立香の情けない『腰ヘコピストン』には存在しないのである。
しかも、今回の締め付けはバーゲストのオマンコが『サイモン様のかっこいい精液を一滴もこぼしたくないです~❤』と無意識に媚びているのだから、余計に強い締め付けなのだ。
立香のような雑魚雄が、幸せな牝の強烈な締め付けに勝てるわけがない。
そこにオマンコが蠢いていき、亀頭を舐め回すようにpenisが刺激されてしまう。
バーゲストが行う逆レイプ中のオマンコよりも気持ちいいかもしれない、それほどの刺激だった。
「あぁっ!? 射精るっ!? 射精るぅぅっっ!?」
びゅるる、ぴゅる、ぴゅぅぅ~~……!
「…………終わりましたね」
「あぅ、うわぁ……!?」
『オレの勝ちだナ』
そんなオマンコの前に、半分だけで射精した状態で射精をしてしまった。
あまりにも情けない三擦り半射精、秒殺である。
バーゲストはやはり冷めた目と冷めた声で、ぐぐっと立香の薄い胸板を押してpenisを無理矢理にオマンコの中から追い出していくのだ。
すると、
当然、立香の射精したばかりのザーメンである。
サイモンのネバネバで白濁というよりも黄色がかった色の濃厚な精液が、このようにサラサラとした真っ白な精液であるはずがない。
そう、サイモンのcockから射精されたザーメンは一滴たりとも流れなかったというのに、立香の射精されたばかりのザーメンは、バーゲストのオマンコが無意識に拒絶したのである。
わざとではないのだろう。
バーゲストはそのような下衆な人間ではないし、完全にサイモンに心を奪われたわけではないのだから、これはあくまでバーゲストの体が本能的に行ってしまったことなのだ。
「ま、負けた……」
それを尻餅をついた状態で見つめていた立香は、連続での射精をヒリヒリと痛むチンポを丸出しにした状態で、ついに現実を受け止めてしまった。
このセックス勝負、手も足も出ずに完敗してしまったのだ。
『No! それはオレとリツカの勝負だロウ? オレたちのFightハ、オレの勝ち。でも、もう一つの勝負ハ、どうカナ?』
「……え?」
「どういう、ことですか……?」
だが、そこでサイモンが『NO』を突きつけた。
確かに、女に翻弄されない射精の耐久勝負ならばサイモンの完全勝利だろうが、男の器としては射精を我慢できるなんていうものよりもずっと大事なことがあると、サイモンは言うのだ。
疑問の顔を浮かべている立香とバーゲストに対して、サイモンは立香と歳がそう変わらないであろう甘いマスクのまま言葉を続けていく。
『オレとバーゲストの勝負サ! オレはバーゲストの心を奪えたノカ、それともリツカに愛を捧げたままなノカ……! そこが男として、本当の勝負ダロウ?』
そう、大事なのは抱かれた女がどう感じたのか、ということだ。
バーゲストを堕とすつもりで本気で抱いた。
聖杯の力がなくとも、この特異点に来る前から性豪のヤリチンとして多くの女性をセックス奴隷に貶めてきたサイモンは、その上で聖杯の力を使って犯したのだから、たった一度のセックスだとしても落とせないのならば、それは敗北以外の何者でもないのだ。
そして、自信もある。
バーゲストの反応からサイモンへの好意を抱いており、逆に立香に対して人間以下の黄色い猿として蔑んでいるということがわかるのだ。
『さぁ、セックス勝負は二本先取したケド、本当の勝者はバーゲストに選んでもらおうカ。ここで人類最後のマスターくんが勝てタラ、カルデアの介入を認めてやるヨ。いや、聖杯だってあげてモ良イ。オレは、女を気持ちよくするノニ自信があル。だから、ここで負けたらオレの完敗ってコトサ』
「え……?」
『リツカとオレの男としてノ差はハッキリしたケド、実際のところ、男の魅力ハ女の心ヲ手に入れられるカ……そういうことダロウ?』
「そ、それなら……!」
一方で、立香は絶望に染めていた心の中に光が差し込むのを感じた。
手コキでもセックスでも先に射精をしてしまった立香が項垂れているところで、サイモンがこんな、負けるわけがない提案をしてきたのだから当然だろう。
これならば勝てると立香は思った。
バーゲストに真の勝者を選んでもらうという話になって、自分が負けるはずがない。
サイモンとのセックスでバーゲストは信じがたいほどに快感を覚えていたが、それでもバーゲストは誇り高く愛情深い、立香をマスターと慕い、恋人として愛を誓い合った妖精騎士なのである。
そのバーゲストが、立香ではなくサイモンを選ぶなど、立香にとってはありえないのだ。
「バ、バーゲスト! さあ、選んで!」
『選ぶんダ、このHoly Grailヲ持って、どちらの手を取るかをナ』
バーゲストに聖杯が手渡される。
そして、立香とサイモンは二人に向かって手を差し出してくるのだ。
どちらの手を取るのか、バーゲストが選ぶ。
選ばれたほうが勝者となり、立香が選ばれれば聖杯を回収してこの特異点の問題は解決し、サイモンが選ばれれば彼にとって都合のいいこの特異点は維持される。
サイモンの『オレが勝てる』という考えも、立香の『俺を選んでくれる』という考えも、ある意味ではどちらも正しいだろう。
バーゲストはサイモンとのセックスで自分が壊れるほどの強烈な快感を覚えた上にここが異常な法則が敷かれている特異点である以上、サイモンを選ぶ可能性は十分にある。
同時に、バーゲストは立香に対して貞操と忠誠を誓った、深い絆を育んだサーヴァントでもある以上、快感に流されることなどなく立香を選ぶ可能性だってあるだろう。
第三者からすれば、バーゲストがどちらを選んでもおかしくはないのだ。
「私が、選ぶのはぁ……❤」
その選択を唯一決めることが出来る、聖杯を持ったバーゲストが、ゆっくりと手を伸ばしていく。
その手が伸びた先に居た男は――――。
「やった、バーゲスト……!」
――――藤丸立香であった。
立香の顔が喜色ばんでいく。
サイモンとのセックスで喘ぎ、媚びるような顔を見せていたバーゲストを見ていると実際のところは少々不安なところがあった。
このまま、バーゲストがサイモンに奪われてしまうのではないか。
それこそ、あの動画の中で黒人男性に組み敷かれていた女性たちの中にバーゲストが加わるのではないかと、心配していなかったわけがない。
立香もまたその伸ばされたバーゲストの手を取ろうとした、その瞬間だった。
バーゲストの手が立香の手をすり抜けて、彼の胸元まで突きつけられる。
その際に、ゆっくりと指が伸びていた開手の状態から、指が閉じた拳の形に変わっていく。
そして、その拳を立香の胸板へと当てて、押すように力を入れたのだ。
「えっ……うわぁっ!?」
呆気にとられていたことに加えて、バーゲストの膂力だ。
押す程度の力しか入れていないはずなのに、ジンジンと激しく痛む腹を抑えながら、立香は地面へと叩きつけられてしまう。
苦痛に顔をしかめながら惨めに床へと尻餅をついて、呆然とした顔でバーゲストを見上げる。
そこには、敵としてブリテン異聞帯で相対した時でも見ることがなかった、冷たい目をしたバーゲストが立っている。
心と体に同時に衝撃を味わったことから、言葉を発することも出来ずにパクパクと口を開閉させている立香に向かって、バーゲストは冷めた目のまま口を開いていく。
「私はサイモンを……サイモン様を選ぶに決まっているだろう。むしろ何故、貴様のような愚鈍で貧弱な黄色い猿を選ぶと、思ったのだ」
「だ、だって! バーゲストは、俺の恋人で……!」
「ああ、そうだったな……私の人生で最大の汚点だ。カルデア式の召喚システムだったか? アレに魅了の魔術の類があるのではないか? そうでなければ、貴様のような吹けば飛ぶ、男とは到底思えない軟弱な存在に胸を高鳴らせるはずがないからな」
そこから飛び出た言葉はあまりにも衝撃的な言葉だった。
サイモンのことを『サイモン様』と熱の感じる言葉で呼び、先日、いや、つい数時間前までは立香のことを熱のこもった目で優しさと愛情に満ちた声で『マスター』と呼んでいたのに、その正反対の声色と冷たさで見下しているのだ。
しかも、自身が立香と恋人としていたのはカルデア式の召喚システムによるなんらかの『精神操作』だったのではないかとまで言ってきたのである。
信じられない。
そんな立香へと視線を外して、バーゲストは聖杯を抱えたままサイモンの手を取った。
立香のように殴りつけるために腕を伸ばしたのではなく、今度こそ本当にその手を取るためである。
「あ、あぁ……!?」
「サイモン様……❤ バーゲストは、あなたの女となります……❤ あそこの間の抜けた顔をした、痩せっぽちの黄猿から私を救い出してくれたこと、感謝いたします……❤」
『いいゼ。お前をオレの女とシテ受け入れるゾ、バーゲスト』
「あぁっ❤ ありがとうございます、サイモン様❤」
そのまま片膝をついた騎士が忠誠を誓う姿勢となり、サイモンへと愛の言葉を囁いていく。
それを受けたサイモンは偉そうにバーゲストの忠誠と愛を受け取ると、バーゲストはその瞳から涙を流すほどに歓喜に震える。
それら全てが、本来はバーゲストから立香へと捧げられて然るべきだったものだ。
奪われてしまった事実を突きつけられた立香は、涙を落とす。
バーゲストは歓喜の涙をこぼし、立香は苦悶の涙を落としていく。
「では……この与えられた聖杯を、利用させていただきます❤ 目をくらまされていた私が、あの黄色い猿からサイモン様へと、正しい形で主を変えられた証明として……バディ・リングを作らせてもらいます❤」
『Oh! 聖杯が指輪ニ……? そんな使い方モ、出来るンダな』
バーゲストに抱えられていた聖杯が形を変えていく。
魔術についてまるで無知であったサイモンは、聖杯の形で聖杯を手に入れたため、その形を変えるという方法さえ思いついていなかったために驚きに顔を染める。
一方で、聖杯が膨大な魔力が形になったものだと、今までのカルデアでの任務で知識を持っていたバーゲストは、それを願えば形を変えるということを良く知っているのだ。
そして、バーゲストが望んだ形は――指輪、バディ・リングである。
「あるべきものをあるべき場所へ……私の心を卑劣に縛り付けていた銀のリングは、その主に返してさしあげましょう」
バーゲストは自身の左手薬指につけていた銀のバディ・リングを外し、代わりに聖杯で創り出した金のバディ・リングをはめ込んでいく。
そして、残った銀のバディ・リング、すなわち藤丸立香と愛を交わしていた、バーゲストにとっては消し去りたい屈辱の記憶の象徴であるそれを手にとって、尻餅をついている立香へと近づいていき、そのリングを立香の『ある場所』へとはめ込んでいった。
「へ、うわ、や、やめて! そんなところに嵌めないで、くぅぅっ!?」
「…………私の薬指にハマっていたリングがピッタリと嵌るとは、本当にお前とサイモン様は同じ男なのですか? いえ、今のはサイモン様に無礼が過ぎましたね。極東の島国で泣きわめく黄色い猿が、このように心身ともに優れた人種である黒人男性のサイモン様を比較するなど、あまりにも不敬というものです。どうぞお許しください、サイモン様」
「な、なんで……なんでぇ……!?」
立香はそのまま泣き出しながら、ひたすらに『何故』とバーゲストへと問いかける。
かつての恋人がそんな哀れを誘う姿を見せても、バーゲストの心は揺るがない。
感情など欠片も感じない冷めた声で、淡々とバーゲストにとっての事実を立香へと告げていくのだった。
「立香よ、はっきりと言いましょう。私はお前のような哀れで惨めな男を愛することなど出来ません。今の私の恋人は、主は、サイモン様です。このような素晴らしい人間を知ってしまえば、どうしてお前のような情けない男に情を向けることが出来るでしょうか。それぐらいは、愚鈍なあなたでもわかるでしょう?」
『そういうことダヨ。男ナラ愛した女の幸せヲ祝ってやりナ』
「あっ❤ サイモン様……んぅっ、ちゅぅぅっ❤ い、いけません❤ 私の唇は先ほどのフェラチオで汚れて、んぎゅぅぅぅっっぅ❤」
『だからなんダ? それぐらいデ、オレのお楽しみヲ邪魔するナ』
「も、申し訳ありませぇん……❤ どうぞ、哀れな奴隷の唇を、お楽しみくださいぃ……むちゅぅぅっ❤」
そのバーゲストの決別の言葉に合わせるように、サイモンはバーゲストの体をぐいっと引き寄せて、その唇を貪っていく。
最初は、先ほどフェラチオをして精飲をしたばかりで汚れた唇であることを理由にキスを拒もうとしたバーゲストだったが、そんなものは関係ないとサイモンはバーゲスト唇へとむしゃぶりつくのをやめようとしない。
むしろ、『汚れた唇なんて気にしないの、すっごく男らしくてかっこいいぃ……❤』などと牝の心を満たされた顔をしてキスに夢中になっているほどだ。
「んちゅぅう、じゅるるるっ、ちゅぅぅっ~~❤ れろぉ、れろれろぉぉっ❤ あぁっ、サイモン様❤ 愛していますぅぅっ❤ ちゅぅぅぅぅっ、ちゅぅ、れろれろぉぉぉんっ❤」
「あっ、あぁぁぁっ!? やめろ、やめろやめろっ! やめろぉぉおっっ! れ、令呪を持って命じる! バーゲスト、正気に戻れ!」
舌と舌でセックスをするような熱烈なキスを見せつけられた立香は発狂した。
目を血走らせて右手を掲げて、その手に刻まれた令呪を使用してバーゲストが正気に戻るように命令をしていく。
「はむぅぅっ❤ ちゅっ❤ ちゅぅぅっっ❤ れろぉぉぉっ、じゅるるるっ❤」
「な、なんで……令呪で命令をしてるのに……! 効果は弱いけど、命令権はあるってダ・ヴィンチちゃんが言ってたのに……!」
だが、バーゲストとサイモンのキスは止まることはなかった。
確かに、カルデアの令呪には、冬木の聖杯戦争などに存在した『絶対的命令権』は存在しない。
あくまで魔力によるブーストがメインとなる、サーヴァントと繋がっているマスターを通じて行えるサポート用の魔術でしかない。
それでも令呪は令呪だ。
命令を受けたバーゲストの動きを、少なくとも緩める効果はあるはずなのに、むしろ令呪による命令が発せられてからのほうが動きが激しくなったではないか。
それは、命令が良くなかったからだ。
立香はバーゲストに対して『正気に戻れ』という命令を行ったのだが、バーゲストは今、間違いなく正気なのだ。
正気のまま、サイモンのことを愛して、嬉しそうにキスをしているのだから、そのような命令で動きが止まるはずがない。
「うわあぁぁぁっ! やめろぉ、『キスをやめるんだ』! バーゲスト!」
「んじゅるぅぅ❤ ちゅぅ……ぅっ!? ちっ……本当に面倒なっ……!」
そのため、今回の単純な動作を遮る命令は効果があったようだ。
バーゲストは眉をひそめて、忌々しそうに立香をにらみつける。
今まで立香が見たことのなかったバーゲストの顔だった。
「……そうですね、では、三本目の勝負をしましょうか。フリースタイルですので、私が種目を決めさせてもらいましょう」
気持ちよかったサイモンとのディープキスを止められたバーゲストは、どうやらひどくご立腹のようだった。
歯を剥き出しにした肉食獣のような恐ろしさを体中から感じさせながらも、淡々とした口調で立香へと語りかけていく。
そうして、その長い脚を、ビキビキに筋肉で包まれた、長くて太い脚を動かしていくのだ。
バーゲストの足裏が、シルバーリングに包まれた立香の情けないpenisに触れた。
足コキである。
「あぅっ!?」
「なんとも情けないペニスでしょうか……こんなものを女に挿入するなんて、女たちに申し訳ないと思わないのですか? あなたにはオマンコではなく、足がお似合いですので……人類最後のマスター、藤丸立香の三本目は足コキでの勝負となります」
「ひぎぃぃ、い、いたいっ❤ リングがチンポに閉まってきて、うぐぅぅぅっ!?」
手コキをするようにバーゲストの足裏がナデナデと立香のpenisを撫でていく。
そんな反応だけで立香のpenisはみっともなくも勃起していき、すると当然、penisにはめ込まれたシルバーのバディ・リングがギチギチと締め上げてくる。
バーゲストの足裏でpenisを撫でられる快感と、バディ・リングで締め上げられる苦痛が同時に襲いかかってくるのだから、立香は涙を流しながら喘ぐほかなかった。
「もちろんっ❤ サイモン様にはそのような無礼なことをしません❤ サイモン様の三本目の内容は、先ほどと同じセックスです❤ どうぞ、私のオマンコを再びお使いくださいませ❤」
『OK! たっぷりと楽しませてもらう……ゼ!』
ずぶ、ずぶずぶ、ずぶりゅぅっぅぅっ! ぬぷぬぷ、ずぶぅぅぅっ!
「おほぉぉぉぉぉっぉ❤ きた、きたぁぁぁっ❤ サイモン様の大きな肉棒が、私のオマンコにぃぃ❤」
一方で、サイモンに対しては媚びるような笑みを浮かべて、セックスを提案する。
立香が足コキしているすぐそばで、サイモンがいきり立ったBig Black Cockをバーゲストのマンコへと後ろから挿入していく。
バーゲストが足を伸ばして立っている状態で、そのまま後ろから挿入するというのは、身長も足の長さも大きく違う立香では絶対に出来ない体位であった。
「ほぉぉぉ、ぉぉぉっ❤ オマンコにcockがイッたりきたりしてぇ❤ う、裏返るっ❤ オマンコが外に出てぇ、体が裏返ってしまうぅっ❤ ほぉ、んほぉぉぉっ❤ イグッ、イグイグっ❤ オマンコイグゥぅぅっっ❤」
『バーゲスト、お前は最高の女ダ! 最高の体ニ、最高の顔! オレの女に相応しイ!』
「あ、ああぁ……ふぎゅぅぅ、ぅうぅ……!?」
犯されて幸せそうに喘いでいるバーゲストを、おざなりに足裏でpenisを撫でられている立香が見上げる。
その顔は、一度として立香が見たことのない、女の幸せに浸っている姿だった。
敗北だった。
自分のすべてが奪われたと認識し、その認識をすると、途端に立香が持っていた聡明さが復活してくる。
「ぜ、全部……奪われてたんだ……なんで、気づかなかったんだ……あの映像も、フェイク動画で……本当に、アルトリアだったんだ……!」
元々立香は愚鈍ではないのだ、この特異点の影響を受けていたに過ぎない。
自分が見たいように見るという、人間ならば誰もが持つ悪癖が特異点の影響で強まってしまっていた。
バーゲストを目の前で奪われた姿を見て、それならば自分の女たちも同じように奪われるはずだという事実に気づいてしまったのである。
源頼光も、アルトリア・ペンドラゴン[ランサー]も、虞美人も、カイニスも、モードレッドも、マルタも、みんなが黒人男性に奪われたに違いない。
「あぁっ❤ もうあんな男に触れたくもありません❤ 私の体に触れるのはサイモン様だけ❤ 私が触れる男の体も、サイモン様だけ❤ 見、見てください❤ もう私の足なんて動かしてないのにっ❤ あ、あの男は腰をヘコヘコと動かして、自分から足裏に擦りつけているのですよ❤ こんな情けない男に、視界にも入れたくありません❤」
「え、あ、ああ……!?」
「笑えますね、『元マスター』❤ あれほどの戦場を駆け抜けた人類最後のマスターが❤ 今では黒人男性様に自分の女を奪われてオナニーをするような、情けない猿以下の存在に成り下がるとは❤ はは、はははっ❤ 嫌悪も一周回ると笑いに変わるとは、あなたに初めて教えられましたよ❤」
気づけば、バーゲストの足の動きは止まっていて、立香の腰がひとりでに動き出していたのである。
もはや足コキではなく、バーゲストの足にpenisを擦り付けるオナニーになってしまっていたのだ。
あまりにも惨めな状態で、立香は涙を流し――同時に、射精をしてしまうのだった。
「うぅぅっ、うぅ、うぅっ!?」
ぴゅっ、ぴゅぅぅ~~……!
こぼれ落ちる涙と一緒に、思わず精液が漏れ出した。
射精に合わせてpenisはしなしなと萎んでいき、先ほどまでpenisを縛り付けていたバディ・リングが生み出す痛みから開放される。
なのに、立香の胸は傷んで仕方なかった。
もう、自分には何も残されていない。
残されているように見えるものも、結局は未来で黒人たちに奪われていくのだとわかってしまった。
「あぁぁっ、ふぅぅっっ❤ こ、これで、三本目もサイモン様の、勝利ィィっ❤ サイモン様の完全勝利でぇ❤ 人類最後のマスターの完全敗北ですっ❤ はぁ、ぁぁっ❤ もっと、もっと突いてくださいっ❤ 勝負なんて関係なく、もっともっと、バーゲストを抱いてくださいませぇ❤」
『Yes,バーゲスト! そんな雑魚雄なんて放っておいて、一緒にイクんだゾ! オレのcockをしっかりと覚えるンダ!』
びゅるるるるっ! どびゅるるっ! びゅっるうっ! どっぴゅぅうぅぅぅぅぅっ!
「ふぎぃっぃぃっぃっぃっ❤❤❤❤ イグッ❤ サイモン様と一緒に、イグゥぅぅっっ❤」
射精が行われる。
本来ならば、立香だけが注ぎ込めるはずだったバーゲストのオマンコに、立香ではない黒人男性の精液が注がれていっている。
もう、立香には耐えきれなかった。
「バーゲスト……頼む、お願いだ……」
すぅ、っと。
右手を捧げる。
令呪における命令は三度行えるため、残った一角を用いて、バーゲストへと命令を――いや、懇願を行っていく。
それは、先ほどのようにみっともなくバーゲストに縋り付く行為ではなく、負け犬が行う白旗宣言だった。
「バーゲストに、命じる……お願いします……俺の頭から……この特異点のことを消して、消してください……聖杯の力で、全部忘れさせて……もう、無理なんです……」
こんなこと、覚えていたくもない。
全てを忘れてしまいたい。
そう思って、聖杯を所有するバーゲストへと記憶抹消を懇願したのである。
「あっ……」
立香の意識が失っていく。
それは令呪を受けてバーゲストが聖杯の力を使用したからだということがわかった。
目が覚めれば、自分はバーゲストたちと恋人であったことや、その恋人たちが自分とは比べ物にならないほどに肉体的に優れている黒人男性に奪われたという事実を忘れていることが出来るはずだ。
立香が安堵しながら意識を失っていく中で、最後に見えた光景は、バーゲストが笑う姿だった。
「良いでしょう、マスター❤ ただし……私なりの改良を込めて、その願いを叶えてあげましょう❤」
だが、立香の望みは叶わない。
黒く染まった聖杯が、黒い男とその奴隷たち以外に、まともな形で願いを叶えることはない。
今回もそうだ。
立香の懇願は、当たり前のように受け入れられ、当たり前のように捻じ曲げられる。
黒人男性様の動くバーゲストは、この哀れで貧弱な、黄色い猿と蔑む男を『猿回しの猿』として見世物にすることに決めたのだから。
◆
「………んっ、あれ、寝てたのか」
立香はビーチにあるベンチの中で目を覚ました。
どうやら、夏の砂浜が心地よくて眠ってしまっていたようだった。
ゆっくりと立ち上がり、大きく伸びをする。
「う~ん……って、メッセージアプリに連絡が来てるな。誰だろう」
ポケットに入れてあった携帯端末を取り出す。
これはカルデアから支給されたもので、マスターである藤丸立香はもちろんのこと、サーヴァントたちや職員たちも所有しているもので、様々な方法で交流を行うための道具として使われているのだ。
その中の一つ、ほぼ全員が使用しているメッセージアプリに、自分宛てのダイレクトメールが送られてきていることに立香は気づき、それを開いていく。
「うわっ!? す、鈴鹿!? な、なんて際どい写真を送ってくるんだ……!」
そこにあったのは、鈴鹿御前がセクシーでありつつ愛らしさが残った、ピンク色のヒョウ柄というビキニ水着を身に纏っていた。
しかも、普段は染み一つない見事な美白肌の鈴鹿なのだが、水着に霊基をあわせた影響か見事な日焼けした褐色肌になっているのである。
しかも、ただの水着姿ではない。
カメラに覗き込ませるようなアングルで、胸元を見せつけるようにして、しかもピンク色の乳輪が覗き込めるのではないかと思うような写真なのだ。
『どうどう、マスター! しっかり見といてね~! マスターにだけ見せる特別な……胸チラ❤』
「す、鈴鹿……本当に、もうっ……! 田村麻呂さんに一途なくせに、こういうことやってくるんだから……!」
鈴鹿御前は立香のハーレムメンバーではない。
生前の運命である、坂上田村麻呂に操を立てているのだ。
それなのに、時々からかうようにこんなセクシーな写真を送り付けてくるのだから困ったものである。
もっとも、そのセクシーな写真を送られて
『それから伝言! レイシフトの調子が悪くて追加も来れないみたい! それも結構時間! ……ってことはさぁ❤ この特異点さっさと解決したらその分遊び放題ってことじゃん! マジでテンアゲ~❤』
そして、業務連絡も忘れていないそのダイレクトメールは、鈴鹿御前という美女がギャルとして天真爛漫な姿を見せていても性根が真面目なことが現れていた。
レイシフトに影響があり、後援の部隊乗り込んでくることも、逆にこちらが逃げ出すことも出来ないようだった。
「そっか……じゃあ、のんびりしようかな……後で、黒人の人達にも挨拶しとかないと。アルトリアとか、バーゲストとか、あんまり仲良くなったけど俺のサーヴァントが仲良くしてるからな。本当は、俺がアルトリアやバーゲストたちと仲良くなりたかったけど、フラレちゃったから、仕方ないよな……」
それを受け入れた立香だが、当然、今までの立香とは別人のような存在に変わっていた。
バーゲストが行った聖杯による記憶操作。
それはただ記憶を消すだけではなく、立香の性格に大きな影響を及ぼしたのである。
とは言え、植え付けられたものはそれほど多くない。
まずは、『奪われた女性たちを忘れたい』と立香が望んだ通りに、『黒人男性の牝となった女との想い出を忘れる』ということを聖杯による力で行われていた。
ここで終われば立香の願いを叶えてやっただけなのだが、しかし、バーゲストは立香を黒人様が楽しめる玩具となれるように、後幾つか『仕込み』をしていたのである。
その一つが、『藤丸立香は好きな女が黒人に奪われることに性的な興奮を覚える』という、寝取られマゾ性癖の完全な定着である。
それ以外では快感を覚えられないというほどに、寝取られることでしか興奮できない、どうしようもない変態に聖杯の力で変えられてしまったのだ。
しかも、恐ろしいことにこれは無意識での性癖なのだ。
立香は自分は普通の人間だと思っているため、普通の恋愛をしようとするが――その結果で結ばれたセックスはちっとも気持ちよくなく、黒人に奪われたときにだけ強い興奮を覚えるのである。
そして、もう一つは『藤丸立香は黒人男性に連れ去られるのを喜んで受け入れる』というものだった。
これを自然なものとするために、『藤丸立香は黒人男性に強い信頼を抱いている』とも植え付けられている。
そこから、『ああ、大好きな女の子が他の男に奪われた……でも、黒人男性なら仕方ないな』という考えはもちろんのこと、『でも、俺なんかよりも黒人の男の人のほうが幸せにできるよな……』という考えまでしてしまうほどだった。
「ぅぅ……こ、これ、ちょっと刺激が強すぎるな……! 後でオナニーをしておこう……!」
そんな改変を行われた立香は、のん気にセクシーな鈴鹿御前の自撮り写真を見て股間を抑える。
先走り汁が今にも溢れだしてズボンの前を汚してしまいそうなエロさだった。
こんな女と恋人同士になればと思いオナニーをすれば、それは気持ちのいい射精が出来るだろう。
そんな期待で、ついにみっともなくカウパー液が漏れ出してしまう。
「……あれ? な、なんで泣いてんだ?」
だが、流れ出たものは先走り汁ではなく、涙だった。
何故かはわからない、哀しいわけでもない。
だけど、涙が止まらなかった。
「とにかく、寝よう……明日のために、明日の明日のために……」
しかし、その『明日』は今までの『明日』とはまるで違うものだ。
黒人男性様が女を抱く明日、そのまた明日も黒人男性様が女を抱くための明日だ。
聖杯で記憶を消されてもなお残るものというものはある。
それを知っている立香は涙を流した。
怒りからでも、屈辱からでもない。
ただ、あの最高の女たちを抱けないことが悔しくて涙を流している。
醜悪な欲望から生まれる、醜悪な涙なのである。
この黒く染められた特異点は、藤丸立香という少年の卑しい部分を強調させてしまったのだ。
終わりのない明日のために、今日は続くのだった――――。
◆
あえぐ、あえぐ。
雨のように、涙のように。
きえる、きえる。
塵のように、嘘のように。
女の望みは満たされず。
今も弱い股間で誤魔化しを。
でも、それも後少しの辛抱だ。
新たに拓いた海の傍、救いの王様たちが現れる。
肉竿と蜜壺を結びつけ、女を救う真っ黒な男たち。
はじめは暗くて黒い光でも、偽物の弱い光に目が眩んでも。
渦に飲み込まれる魚のように、惹かれ合う。
淫らな砂浜、汚れた街。
偽りの愛を退けた後に、ついに救いは迎えられる。
港は渚に戻るけど、偽物は深い深い地の底へ。
黒き肉の竿を振りかざし、異邦の旅人を踏みつけて。
救いの男たちは、玉座に腰かける。
星見の砦は地に堕ちる。
黒き竿を掲げて王様たちが現れる。
ハレムに君臨するのは真の王様たち。
淫らな冠、おひとつどうぞ。
罪を知らぬ偽物に、落とされるのは女の御足。
ならせ、ならせ。
雷のように、波のように。
多くの女を鳴かせて示せ。
真の王様たちのお城を作れ。
くろいぬの女も捧げた後に。
きつねの女も奪われた後に。
役目を終えた『マスター』は、新しい役目にさようなら。
仕事はちょっとなまけるけども。
私たちは淫蕩な悪女の裔(すえ)。
心はずっと欠けたまま。
気持ちがいい明日がほしいのさ。
(終)

