俺達が巨人にもてあそばれる話(後編) (Pixiv Fanbox)
Content
前編はこちら!
俺達が巨人にもてあそばれる話(前編)
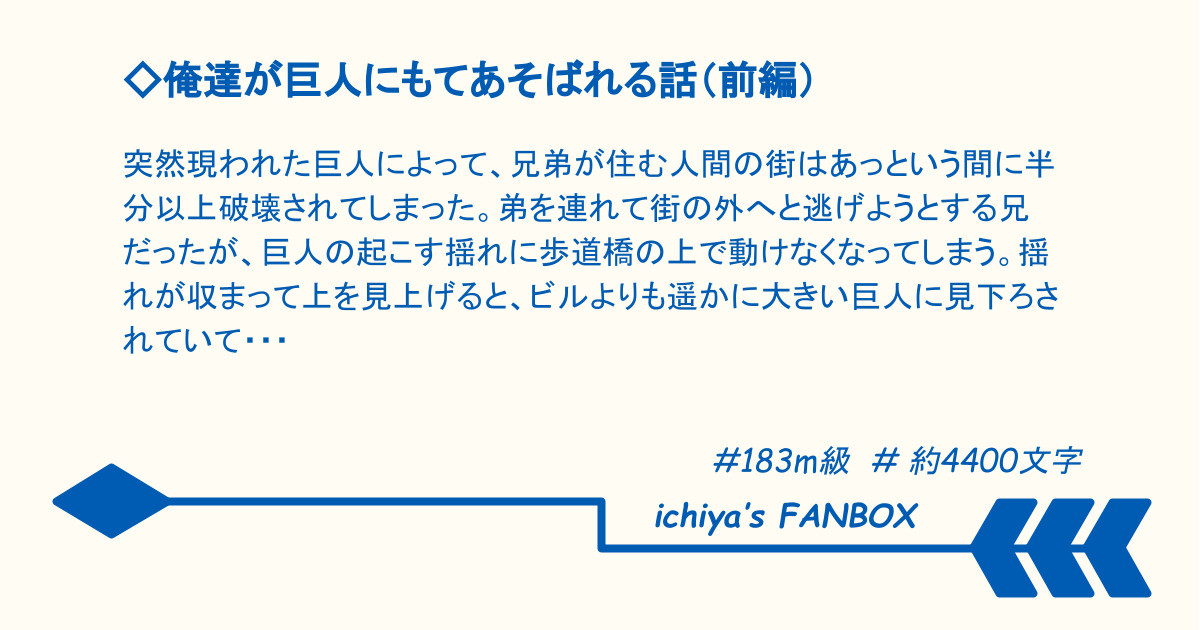
巨人がやってきた。 「にいちゃん……!」 「トウタ、急いで……!!」 弟の手を引いて、街の外へと向かって走る。郊外へ続く大通りは道路を埋め尽くすように車が乗り捨てられ、ところどころ炎が上がっている。周囲に人はいない。最初のパニックではぐれた弟を探していたら、逃げ遅れてしまった。でもそれも仕方ないと思...
周りを見ると、このビルより高い建物はない。だからこのビルはこの辺で一番高いビルのはずだ。なのに、今目の前に見えるのは巨人の黄色い水着……つまり、股間部分だ。10階以上のビルだろうに、それは巨人の股間にも届かないのだ。どんなデカいチンコが入っているのか、水着はもっこりと前に大きく膨らんでいて、それだけで大きな影を作っている。
車が駐車できそうなボコボコの腹筋に、雨宿りができそうなほど張り出した胸板。その上から見下ろしてくる、巨大な顔。何回も見上げて、ようやくその顔が男前だということに気づいた。だから何だという話だけれど。
「うわ……あっ!」
巨人が動き出した。それだけで地面と一緒にビルがグラグラと揺れる。巨人がしゃがみ込んでいるようで、股間がビルの下に隠れ、目の前に腹筋が現れる。それも下がって、人間どころかバスが挟めそうな深い谷間の大胸筋が現われた後、今までで一番の揺れが俺達を襲った。ビルの屋上から放り出されるほどの揺れ。俺とトウタは勿論だが、何百キロかはありそうな歩道橋の通路すらもビルの上で跳ね回っている。ようやく揺れが小さくなった時、斜めにある古いビルがゆっくりと崩れて行くのが見えた。この揺れで崩壊しているのだ。そしてその揺れを起こしたのは、もちろん。
(ち、かい……)
さっきの揺れは、この巨人が地面に座り込んだことで起きた揺れだったのだ。そして座り込んだのにもかかわらず、巨人の胸半分から上はビルの上からはみ出している。でも揺れはまだ終わらない。巨人が脚を伸ばすと、このビルの両側にあった低いビルが積み木のように蹴倒されて、崩れるより先に吹っ飛んでいく。そのまま巨人が脚を曲げて胡坐をかくと、ぐぐっ、と巨人の身体が近くに来る。このまま押し潰されてしまいそうだ。
「こっちの方が話しやすいだろ?」
轟音が、先ほどよりずっと近いところから響く。座り込んでもビルよりでかい巨人に見下ろされている。胡坐の中に囲われるように俺達のいるビルは閉じ込められた。巨人の前じゃどんな建物でも頼りなく見えてしまう。現にこのビルも、巨人はほとんど触れてすらいないのに屋上の床のいたるところからひび割れてきている。
「ひっ!」
巨人の腕がググっと持ち上がって、小さな家ぐらいもありそうな手がこっちに来る。それだけで風が吹き、トウタを抱きしめながら体を縮こまらせた。だが巨人の手は俺達ではなく、もうぼろぼろになった歩道橋の通路を掴み上げた。そして巨人はそれを手の中で、まるで紙屑にでもするように握りつぶしていく。金属が折れ曲がり、コンクリが砕ける音が手の中から聞こえてくる。あっという間に歩道橋は巨人の親指と人差し指で摘まめるほどの大きさになってしまった。俺達は数分前まであそこにいたのだ。それに気づいてまた震えが止まらなくなる。
(に、げ)
ビルごと巨人に脚で囲われて、逃げられるわけなんてないと頭ではわかっている。でも恐怖には勝てなかった。なんとかトウタを引っ張り立たせて、ビルの中に降りる階段へ向かう。足が震えてろくに走れもしないが、そんなにドアは遠くない。次の瞬間、ふっと頭上が暗くなる。
(くも……?)
ではないことは、すぐに分かった。顔を上げるより前に、俺達の上を通ったものが階段のあるところに伸びていく。巨人の、手だ。巨人の手でかき回された空気が遅れて後ろから吹き付ける。階段のある、小屋ほどはある大きさのそれが、すっぽりと巨人の手の作る影に覆われてしまう。そしてその手が下に降ろされると、本当に、本当にあっけなくそれは崩れてしまった。手が階段の建物を押し潰した衝撃でビルが揺れ、俺達は尻もちをつく。土ぼこりが収まって見えたのは、瓦礫の山。もう下にも降りられない。巨人の手が空気を巻き込みながら引っ込んでいく。それを座り込んだまま目で追っていくと、こちらを見下ろす巨人と目が合った。もう逃げられない。助からない。俺達は、このまま……
「にいちゃん……」
下から聞こえる声にはっとする。抱きしめていたトウタは、涙や鼻水でぐじゅぐじゅになりながら俺を不安そうに見上げていた。そうだ。トウタだけでも……ぐい、と服の袖で自分の顔をぬぐう。
「トウタ、ここにいてな」
トウタから手を放して、巨人の方に向き直る。震える足では立てず、座り込んだまま巨人を見上げた。ああ、怖い。でも、俺は、兄だから。這いつくばるようにして土下座の姿勢になる。
「おね、おね、おねがい、が、あり、ます!!!」
緊張と恐怖で声もうまく出ないが、それでも精いっぱいの声量で叫ぶ。
「弟だけ、でも、助けて、助け、てください!」
ゴゴン、とビルが揺れ動いた。ずっと地べたを見ているが巨人が動いているのが押し出される空気でわかる。影が濃くなり周りが暗くなり、上の方にただならぬ圧迫感を感じ、生暖かい、まるで、鼻息のような風が……まさか、とゆっくり上を見上げる。
「ひっ、ああああああ!!!」
叫んでしまった。目の前、本当に二メートルもないぐらいのところまで、巨人の顔が近づいていた。空が巨人の顔で覆われている。まるで天井のようだ。その俺よりずっと大きな目玉が、ぎょろりと俺の方に向いている。漏らしていないのが不思議なぐらいだった。
「ひっ、あっ」
「何だ? もっかい言え」
巨大なスピーカーの最大音量が耳元で響いたような爆音。空気どころかビル自体が震える音圧にとっさに耳をふさいだがそれでも耐えられずぐらっとくる。これでも普通にしゃべっただけなのだろう。とんでもない音量だったが骨に響く低音は何とか聞き取れた。気力を振り絞って真上を向く。涙が目にたまって視界がにじむ。
「お……お、俺はどうなってもいいので……!! 弟は……弟だけは助けてください……!!」
言えた。巨人の目の黒い部分が大きくなる。後はもう、上も見ていられなくてもう一度土下座をした。ぼとぼとと涙がコンクリに落ちて染みになる。本当に、本当に弟だけでも見逃してほしい。巨人の顔が離れていくのを風や影から感じる。土下座の状態のまま顔を上げると、巨人が座っている道路の方を見下ろして腕を動かしているのが見えた。
(……何を……?)
そして巨人が腕を上げると、その指先で摘まんでいたものを俺の近くに置いた。それは、電話ボックスだった。フレームは指でつままれていた部分がべっこりと歪み、外側の透明な板もヒビだらけで真っ白だった。巨人を見上げると、楽しそうな顔で笑っている。
「見てろよ」
巨人が人差し指を電話ボックスの上に乗せた。その指は電話ボックスの倍ほど太い。指の腹が天井に触れるとそれだけでメギッと音がしてフレームがゆがむ。そのまま指はまるで紙でできているかのように容易く電話ボックスを押し潰していく。バキバキバキという音が数秒続いたかと思うと、巨人の指がビルの屋上にくっついて屋上が揺れる。巨人が指を上げると、底にはペチャンコに押し潰された電話ボックスの残骸があった。巨人はそれをぴん、と簡単に指で跳ね飛ばす。
「おら、そこ立てよ」
巨人の声にビクッと肩が震える。見上げると、巨人がさっきまで電話ボックスがあった箇所を指さしていた。巨人の指で押されてコンクリの床自体が大きくひび割れ凹んでいる。
「お前も同じよーに潰してやるから。ああ、どっちでもいいぜ? 残った方を助けてやるよ」
その言葉に、ヒュッと血の気が下がった。弟が助かる、という気持ちの前に巨人の指で無残に潰された電話ボックスの光景がフラッシュバックする。金属でできた電話ボックスであれなのだ。人間など、本当に一瞬でプチっと潰される。
(……でも)
一度大きく息を吐く。震える脚を殴って立ち上がり、後ろで座り込んで泣きじゃくる弟の前にしゃがみ込む。
「うぐっ、えぐっ……」
「トウタ」
「に、い……」
「トウタ、ずっとずっと大好きだからな。……俺の分まで、生きてな」
そのままぎゅっとトウタを抱きしめる。もうこれが最期だと思うと、勝手に熱い涙があふれてくる。何秒たっただろうか。ゆっくりと腕を解き立ち上がる。トウタの手がすがるように伸びてきたが、腰が抜けているのか立ち上がってはこなかった。それを振り切るようにして、巨人の方に向き直る。巨人の指が作った凹みに歩き、躓きながらその中心に立った。ぐいっと袖で涙をぬぐい、巨人を見上げる。
「へえ、お前でいいんだ」
そう、俺でいいんだ。巨人は弟でもいいと言ったが、そんなの、選択肢としてすらない。なんとか、何とか生きてほしい。巨人の腕が動いて、俺の真上に指が影を作る。指紋まで見えるような大きな指。ああ、俺はこれからあれで潰されるのだ。指がゆっくり近づいてくる。体中がガタガタと震え、一歩も動けない。
「あ、あ……」
ついに髪の毛に指が触れる。感じたことのない重量。抵抗など一切できず自然に膝が曲がる。このまま押し付けられて潰れる……と目をつぶる。……が、指の動きが止まった。
「……?」
ぐっと膝を伸ばそうとして見るが、巨人の指は微動だにしない。上に上がることもせずこれ以上も下がらず止まったままだ。どうしようかと悩みかけたところで、急にその指が横にぐわんぐわんと動き出した。
「うあっ!?」
指に押さえつけられていた俺の頭は首がねじ切れてしまいそうだった。巨人の指からすれば少しの動きでも、俺からすればとんでもないパワー。潰れるんじゃなくてこうやって死ぬのか、と思った時にふっとその指が上に上がった。指の影から外れて周囲が明るくなり、こちらをにやにやと見下ろしている巨人の姿が上にある。
(な、なんだ……?)
そう思ったのも束の間で、急に巨人の親指と人差し指が俺の前後に来てそのまま俺を挟んだ。
「ぎゃああああああああ!!!!」
幅だけで俺の身長よりでかい指に挟まれて身体の骨がミシミシときしんでいる。何とか顔は出ているが腕も足も全く動かせなかった。このまま、潰されるのか。そのまま持ち上げられ巨人の目の前に吊り上げられる。
「ひっ、うわっ……!!!」
「お前みたいな健気な奴、俺結構好きなんだわ」
……正直、この巨人が何を言っているのかわからなかった。聞き間違いかとも思った。今も強烈な圧力で身体が潰されそうなのに、殺す間際に好きだとか、何を言いたいんだ。巨人は俺をつまんだまま、手を下の方へと降ろしていく。顔からでっかい胸板や腹筋を通り過ぎて、いびつに膨れ上がった水着の近くまで持っていかれる。ここまで近寄ると巨人の汗のようなにおいが強く漂ってくるが、腕すら動かないので鼻を覆うこともできない。
「ん?」
巨人の声に顔を上げると、巨人はビルの屋上を見ているようだった。そして俺もまた上へと引き上げられ、ビルの屋上を見れるように向きを変えられる。そこで見たのは、ビルの屋上から乗り出して巨人に向かって叫んでいるトウタの姿だった。心臓が跳ね上がる。
「ほ~ら見てみろよ兄の方、弟まで健気だぜ?」
「トウタ、危ない、落ちるぞ! 俺はいいから!!」
フェンスがはぎとられ、巨人が起こした揺れを受けまくったビルは、外側から見るともういつ崩れてもおかしくなさそうだった。必死にトウタに叫ぶもわめくトウタはいうことを聞かない。このままじゃ落ちる――というところで、ビルが大きく揺れて、トウタがコロンとバランスを崩した。
「トウターーー!!!」
全てがスローモーションに見えてくる。そんな。せっかく、せっかくトウタは助かりそうだったのに。助けに行きたくても巨人に摘ままれているこの状況じゃどうにもならない。ただ見ているしかできない自分がふがいなくてボロボロと涙があふれる。そして、急にトウタの落ちる先に巨大な肌色の板が現われた。
「あ……?」
その板は巨人の手のひらだった。俺をつまんでいない、反対の。その手はビルの外壁にあたるとコンクリを破壊しながらビルにめり込んで土煙をあげ、その煙の中にトウタが落ちたように見えた。
「ああっ、トウタ! トウタ!!」
動けもしないのにじたばたしていると俺をつまむ巨人の手が動いて、手のひらの方に寄せられる。そこからぽいっと、3メートルほどの高さから手のひらに落とされた。巨人からすればそっと落としているのかもしれないが相当な高さである。ただ巨人の手のひらは意外に柔らかく、なんとか立ち上がると、土煙に咳き込みながらトウタの名前を呼ぶ。
「にいちゃん……」
「トウタ!! ああ、トウタ!!」
トウタは瓦礫と一緒に手のひらの上に転がっていた。慌てて駆け寄り抱き上げる。奇跡的にけがはしていないようだった。
「お前、なんてばかなことを……」
「うん……ごめんね」
ぎゅうっとトウタを抱きしめていると、上からまた巨人の声がした。「死ななくてよかったな」だと。普通なら怒りもする発言だが、もう、この強大な力を持つ巨人の前では、そんな気も起きなかった。トウタを抱きしめながらその顔を見ていると、巨人がバス並みに太い指で俺達よりでかい手のひらの瓦礫をドゴンドゴンと弾き飛ばしていく。もし俺達に当たれば一瞬でミンチになるだろう。巨人はあらかたの瓦礫をどけ終わると手のひらをぐっと顔に近づけた。その鼻息の暴風で、手のひらの小さな砂粒がまとめて吹っ飛んでいく。
「ははっ、きったね」
笑い声が体中に響く。もう俺達がどうなるのかまったくもってわからない。潰すと言ったり、弟を助けたり、本当に何がしたいんだ。弟と二人で震えていると、急に巨人が立ち上がる。そして、さっきまで俺達がいたビルに軽く蹴りを入れた。凄まじい爆音がして、ビルはばらばらになりながら吹っ飛んでしまった。もし、まだあそこにいたら、という想像をして冷や汗がぶわっとあふれ出る。巨人はそのまま俺達の乗る手のひらを下へと下げていった。すると見下ろした先にあるのは、まっ黄色な競泳水着。
「うわ……」
思わず、息をのんでしまう。巨人の水着はさっきよりも大きく膨れ上がって、いや、いびつに盛り上がっていた。左の腰の方に向かって、まるで電車のようにでかいふくらみがずろんと伸びている。巨人のチンコというのはこんなにもでかいのだろうか。近すぎて熱気や臭いがこっちにまで届いている。巨人が反対の手で水着に手をかけると、その中身が姿を現し、汗とアンモニアの強烈なにおいが一気にこちらにまで押し寄せてきた。とっさに弟を胸にかばい、袖で鼻を覆う。むんむんとした熱気でジワリと汗がにじんでくる。その中身も本当に巨大だった。あのふくらみは間違いなくチンコだった。水着の中が窮屈だと言わんばかりに水着の生地を押し広げながら今にも飛び出さんとビクビクうごめいている。まるで龍のようだ。
「お前ら、これが何かわかるよな?」
巨人の手のひらが、斜めになりながらさらに股間の方に近づいていく。おい、まさか。臭いと熱気が強くなり水着の縁と手のひらがくっつく。そのまま手のひらの角度が急になっていく。踏ん張ったが、駄目だった。俺とトウタは、手のひらを、水着の中、チンコに向かって転がり落ちていく。
「うわあああああああああああああ!!!」
転がりながら落ちた場所は、ごわごわした紐のようなものが敷き詰められていているところだった。少ししてそれがチン毛だということに気が付く。図らずもそれがクッションになったようだが、それよりもサウナのような熱気と吐きそうになるほどの臭いがすごい。巨人は、マジで俺達をパンツの中に放り込んだのだ。チン毛の下にある地面はどくどくと脈打っていて、さっき上から見たチンコの上にいるのだと嫌でもわからされる。
「帰ったらまた遊んでやるよ。兄貴はその間、弟が潰れないよう守ってやれよ?」
上から覗く巨人の顔が、本当におもちゃで遊んでいるようで、なんでか悔しくて泣きそうになる。巨人の指が外れてパンツが閉じられると、熱さと臭いがこもって息が詰まりそうになる。水着越しの黄色い光の中、もう泣きもわめきもしない、えづくように息をしているトウタを強く抱きしめる。
「大丈夫……にい、ちゃんが、守ってやる、から……」
巨人が歩き出すと、地面がトランポリンのように激しく揺れだした。チンコと身体の間に挟まれたら今度こそ本当につぶれてしまう。チン毛に身体をひっかけるようにして耐えようとしたが、急にチンコがずぐんと跳ね上がって、トウタともども吹っ飛ばされる。どこかにまた落ちて、肉が迫ってきて。
「なんなんだよ、もう」
俺の記憶は、そこで途切れた。
END

